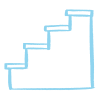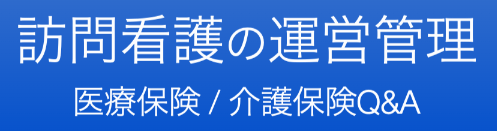口腔・咽頭がんは、食べる・飲み込む・話すといった基本的な機能に影響が出やすいがんで、治療後の後遺症や栄養管理が大きな課題となります。自宅療養では、嚥下障害や口腔内の痛み、声の出しにくさなどへ適切に対応するために、訪問看護による医療的ケアや口腔ケア、訪問リハビリ(がんリハ)による嚥下訓練・発声訓練が重要です。本記事では、疾患の基礎知識から在宅での支援方法、がんリハの具体的な効果まで、専門的な内容をわかりやすく解説します。
Contents
口腔・咽頭がんとは:基本的な知識と理解
口腔・咽頭がんと診断された方、あるいはその可能性があると伝えられた方にとって、まずは病気の正しい理解を持つことが大切です。口腔や咽頭に発生するがんがどのような病態を示し、どのような特徴や種類を持つのかを知ることは、適切な治療法を選択し、これからの生活設計を考えるうえで欠かせない第一歩となります。
口腔・咽頭がんは、舌、歯肉、口底、口蓋、扁桃、咽頭粘膜などに存在する粘膜の上皮細胞から発生する悪性腫瘍であり、発生部位や組織型の違いによって複数のタイプに分けられます。最も多くみられるのは「扁平上皮がん」で、日本人における口腔・咽頭がんの大多数を占めています。このがんは喫煙や飲酒と強く関連しているほか、近年ではヒトパピローマウイルス(HPV)の感染も重要な原因の一つとして注目されています。
発生部位によって症状の現れ方が異なるのも特徴で、舌にできた場合には違和感や痛み、咽頭にできた場合には飲み込みにくさや声のかすれなどが初期症状となることがあります。こうした変化に早く気づき、医療機関を受診することが早期発見・早期治療につながります。口腔・咽頭がんは進行すると生活の質に大きな影響を与える可能性があるため、その病態を理解し、自分に合った治療法を選ぶことが非常に重要です。
扁平上皮がん(口腔・咽頭がんの代表的タイプ)
口腔・咽頭がんの多くは「扁平上皮がん」と呼ばれるタイプであり、日本人に発生する口腔・咽頭がんの大半を占めています。この扁平上皮がんは口腔や咽頭の粘膜上皮から生じ、比較的進行が緩やかな場合もありますが、早期にリンパ節や遠隔臓器へ転移するケースも少なくありません。さらに、このがんは発生部位や進行度、組織学的な悪性度によって分類され、その結果が治療方針の決定に大きく影響します。たとえば、病期の進行状況や病理学的評価に基づき、手術療法・放射線治療・化学療法、あるいはそれらを組み合わせた集学的治療が検討されます。
口腔・咽頭がんを理解することは、単に医学的な知識にとどまらず、日常生活の設計にも直結します。発声や嚥下機能への影響、さらには治療に伴う味覚障害や口腔乾燥、外見の変化などにどう対応するかを考えることは、患者本人の安心や生活の質を守るために欠かせません。そのため、この病気がどのような性質を持ち、どのような治療の選択肢があるのかを正しく知ることは、診断を受けた直後から取り組むべき極めて重要な課題といえるでしょう。
転移しやすい口腔・咽頭がん
口腔・咽頭がんは、特に進行すると骨やリンパ節への転移が非常に多いがんです。骨への転移では、脊椎(背骨)や骨盤、大腿骨などが特に多く見られ、痛みや骨折を引き起こすことがあります。また、リンパ節への転移は全身へ広がる「入り口」となることがあります。肺や肝臓、脳など他の臓器へ転移する場合もありますが、骨転移ほど頻繁ではありません。
頸部リンパ節:
口腔・咽頭がんは、進行すると頸部リンパ節への転移が非常に多いがんとして知られています。特に舌や口底、咽頭の腫瘍では早期からリンパ節転移が起こりやすく、首のしこりとして気づかれることも少なくありません。頸部リンパ節はがん細胞が全身に広がるための重要な通路となるため、ここへの転移は病気が進展していることを示し、治療戦略に大きな影響を与えます。リンパ節転移が確認されると、さらに肺や肝臓などの遠隔臓器へ病変が広がるリスクも高まります。
また、口腔・咽頭がんは骨や肺など他の臓器にも転移することがありますが、最も頻度が高いのはやはり頸部リンパ節です。骨への転移は口腔・咽頭がんのように特徴的ではないものの、進行例では頭蓋骨や胸骨、脊椎といった部位に及ぶこともあり、強い痛みや生活の質の低下を招く可能性があります。
特に進行期に達した口腔・咽頭がんでは、患者の多くにリンパ節転移が確認されると報告されており、その臨床的な重要性は極めて大きいといえます。こうした転移の有無や広がりは、治療法の選択だけでなく、予後を判断する上でも欠かせない要素であり、定期的な検査と適切な対応が求められます。
治療とがんリハビリテーションの重要性
初期の口腔・咽頭がんであれば、腫瘍の小さな段階での切除手術やレーザー治療など、比較的低侵襲な方法で根治を目指すことが可能です。しかし進行がんとなると、部分切除にとどまらず広範囲の切除や再建手術が必要となり、さらに術後に放射線治療や化学療法を併用することが多くなります。咽頭がんでは嚥下や発声に関わる重要な臓器が含まれるため、治療後に気管切開や再建手術を伴うケースも少なくありません。
こうした外科的治療や放射線・化学療法の影響により、嚥下障害、発声機能の低下、口腔乾燥、味覚障害、全身の倦怠感など、日常生活におけるさまざまな課題が生じます。そこで訪問看護や訪問リハビリテーション(がんリハ)が果たす役割は大きく、多職種チームが連携しながら患者と家族を支えます。嚥下機能の改善を目的としたリハビリテーションや誤嚥防止の工夫、必要に応じた経管栄養や食形態の調整、会話や発声をサポートする言語療法、さらには疼痛コントロールや口腔衛生指導といった支援が行われます。また、外見や発声の変化に伴う心理的な負担に対しても、専門職によるカウンセリングやセルフケア支援が提供されます。
これらの支援を通じて、安心で安全な療養環境を整え、症状の悪化防止や生活の質(QOL)の向上を目指すことができます。患者と家族のニーズに応じて、がん看護専門看護師、言語聴覚士、理学・作業療法士、管理栄養士、精神保健福祉士などがチームとなって支援にあたることが、口腔・咽頭がんの療養生活を支える大きな力となるのです。
そこで訪問看護・訪問リハビリテーション(がんリハ)では、多職種チームが連携して以下の支援を行います。
- 嚥下機能のサポート:嚥下リハビリ、誤嚥防止の工夫、経管栄養や食形態の調整
- 発声・会話の支援:言語療法、発声訓練、コミュニケーション手段の確保
- 口腔ケアと栄養管理:口腔衛生指導、味覚障害や口腔乾燥への対応、食欲低下や体重減少予防の栄養指導
- 疼痛コントロール:創部や神経痛へのケア、薬剤の適切な調整と服薬管理
- 体力・ADL(日常生活動作)の維持:歩行練習、上肢・下肢の運動療法、呼吸リハビリ
- 心理的サポート:発声や外見の変化に伴う不安へのカウンセリング、セルフケアの支援
- 家族支援と療養環境整備:介護方法の助言、在宅での安全な療養環境づくり、家族の心理的サポート
これらの訪問支援により、ご自宅での安心・安全な療養環境を整え、症状の悪化防止やQOL(生活の質)の向上を図ります。
もしかして?口腔・咽頭がんの初期症状チェックと進行時のサイン
気づきにくい口腔・咽頭がんの初期症状
口腔・咽頭がんは早期の段階では自覚できる症状が乏しく、健康診断や血液検査で偶然見つかることはほとんどありません。そのため、気づかないうちに進行してしまうケースも少なくありません。しかし、日常生活の中で現れるささやかな変化に注意を払うことで、早期に医療機関を受診するきっかけをつかむことができます。
初期の口腔・咽頭がんでは、口の中やのどに違和感が生じるのが代表的なサインです。例えば、治りにくい口内炎のような潰瘍やしこりが続く、舌や歯ぐきに赤や白の斑点ができる、のどの奥に異物感がある、といった症状が挙げられます。また、飲み込みにくさや軽いしみるような痛み、声のかすれが長引く場合にも注意が必要です。さらに、原因不明の体重減少や慢性的な疲労感が続くことも見逃せないサインとなります。
もしこれらの症状が2週間以上続く、あるいは改善しない場合には、自己判断で放置せず、耳鼻咽喉科や歯科口腔外科を受診することが推奨されます。口腔・咽頭がんは早期発見できれば治療の選択肢が広がり、発声や嚥下といった大切な機能を保ちながら治療に臨むことが可能になるため、小さな変化を見逃さない姿勢が極めて重要です。
口腔・咽頭がんが進行した場合に現れる症状
口腔・咽頭がんが進行した場合に現れる症状については、腫瘍そのものによる局所的な影響と、転移による全身的な症状に大きく分けられます。
局所的な症状
腫瘍が大きくなると、口の中やのどでの痛みが強くなり、食事や会話が困難になります。嚥下障害が進行すると食べ物や飲み物が飲み込みにくくなり、むせ込みや誤嚥を起こすこともあります。また、声帯や咽頭に腫瘍が及ぶと声がかすれるだけでなく、発声が困難になることもあります。腫瘍が進展して顎や周囲の組織に広がると、口が開きにくくなる開口障害や、歯のぐらつき、出血や口臭の悪化といった症状も現れます。
リンパ節や他臓器への転移による症状
頸部リンパ節への転移は口腔・咽頭がんで非常に多く、首にしこりとして現れるのが典型的なサインです。これによりリンパの流れが滞り、腫れや圧迫感を生じることがあります。さらに進行すると肺や肝臓など遠隔臓器に転移し、呼吸困難、慢性的な咳、黄疸、肝機能障害といった全身症状が出ることもあります。脳への転移は頻度は少ないものの、起こると頭痛やけいれん、しびれ、言語障害など深刻な神経症状を引き起こします。
全身的な症状
進行がんでは腫瘍そのものの影響に加え、体全体の状態にも変化が現れます。体重減少、強い倦怠感、食欲不振、貧血など、がん特有の全身症状が出やすくなり、さらに治療の副作用も加わることで生活の質が大きく損なわれることがあります。
チェック後の対応と内視鏡検査の重要性
- 症状の継続期間を確認
症状が2週間以上続く場合は、速やかに専門医へ受診しましょう。 - 医師に伝えるべき情報
- 症状の開始時期・頻度、便通との関係
- 既往の炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎など)
- 家族歴(口腔・咽頭がんやポリポーシス疾患)
- 喫煙・飲酒歴、食生活の特徴
- 検査の選択
- 便潜血検査:スクリーニングとして有効
- 大腸内視鏡検査:ポリープ切除や生検が可能で、早期発見に最も有効
症状がどのくらい続いているかを把握することは、口腔・咽頭がんの早期発見において極めて重要なポイントです。もし口の中の潰瘍やしこり、のどの痛みや違和感、声のかすれ、飲み込みにくさといった症状が2週間以上続く場合には、放置せずに速やかに耳鼻咽喉科や歯科口腔外科などの専門医を受診することが推奨されます。
医師に相談する際には、症状がいつから始まったのか、その頻度や強さ、食事や会話との関係について具体的に伝えることが役立ちます。また、過去に口腔や咽頭に関わる病気を経験したことがあるか、治療歴があるかどうか、さらに家族に口腔・咽頭がんの既往があるかといった情報も診断に重要です。加えて、喫煙や飲酒などの生活習慣や、食生活の特徴もリスク評価において参考となるため、できる限り正確に伝えることが望まれます。
国立がん研究センターの統計によれば、早期に診断された口腔・咽頭がん(ステージI)では5年生存率が90%を超える一方で、リンパ節転移や遠隔転移を伴う進行例(ステージIV)では10%前後にまで低下します。この大きな差は、早期受診と早期治療の重要性を如実に示しています。わずかな違和感や変化であっても軽視せず、医師の診察を受けることが、治療の選択肢を広げ、発声や嚥下といった生活の質を守ることにつながるのです。
口腔・咽頭がんの原因とリスク要因チェックリスト
以下の項目は、口腔・咽頭がんのリスクを高める可能性がある要因です。あてはまるものがいくつあるかを確認し、生活習慣や検診の見直しに役立ててください。
口腔・咽頭がんのリスク要因チェックリスト
- 喫煙習慣:紙巻きたばこ、葉巻、パイプ、噛みたばこなどによる長期的な曝露
- 過度の飲酒:特に強い酒や毎日の飲酒習慣
- 喫煙と飲酒の併用:相乗的に発がんリスクを高める
- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染:特に中咽頭がんの重要な原因
- 不十分な口腔衛生:慢性的な炎症や不適合な義歯の使用
- 栄養不足:ビタミンA、ビタミンC、鉄などの欠乏や野菜・果物不足
- 職業的曝露:アスベスト、木材粉塵、化学物質への長期曝露
- 遺伝的要因:家族に口腔・咽頭がんの既往がある場合
- 免疫力の低下:免疫抑制療法や基礎疾患による抵抗力低下
ストレスとの関係について
ストレス自体が直接口腔・咽頭がんを引き起こす明確な証拠はありませんが、ストレスによる食生活の乱れ(高脂肪・高カロリー食への偏り)、運動不足、睡眠障害が間接的にリスクを高める環境をつくると考えられます。
罹患率と死亡率の男女差
日本における口腔・咽頭がんの罹患率および死亡率は、性別を問わず上昇傾向にあります。国立がん研究センターの統計によれば、口腔・咽頭がんは日本人において比較的多いがんのひとつであり、その罹患率は年齢とともに増加し、特に60歳以上で顕著に高まることが示されています。死亡率は一部の消化器がんや肺がんと比べるとやや低い水準にあるものの、患者数そのものは高齢化に伴って確実に増加しており、社会的な関心が高まっている分野です。
この背景には、加齢による発症リスクの上昇に加え、食生活の欧米化や栄養バランスの偏り、さらに喫煙や飲酒といった嗜好習慣が大きく影響していると考えられます。特に喫煙と飲酒の併用は相乗的にリスクを高めることが知られており、日本における口腔・咽頭がん増加の要因のひとつとされています。また、近年ではヒトパピローマウイルス(HPV)感染が中咽頭がんの重要な発症要因として注目されており、若年層での罹患率上昇の一因ともなっています。
一方で、歯科健診や耳鼻咽喉科での定期的な検診、内視鏡検査などにより、早期発見されるケースが増えていることから治療成績は向上しています。早期に診断された場合の生存率は非常に高く、治療後も生活の質を維持できる可能性が広がっています。
予防のためにできること
- 定期的に歯科健診や耳鼻咽喉科でのチェックを受け、早期発見・早期治療につなげる
- 禁煙を徹底し、過度の飲酒を控える
- バランスの取れた食生活を意識し、野菜・果物・大豆製品・魚などを積極的に取り入れ、塩分や加工肉の過剰摂取を避ける
- 週150分程度の有酸素運動を目安に、無理のない範囲で継続的に体を動かす
- 適正体重を維持し、糖尿病や高血圧など生活習慣病をコントロールする
- 十分な睡眠とストレスケアを心がけ、免疫力を保つ生活習慣を整える
- 家族に口腔・咽頭がんの既往がある場合やリスク要因が重なる場合には、早期から専門医に相談し、定期的な検査を受ける
口腔・咽頭がんは生活習慣と深く関わるがんです。自分でコントロールできるリスク因子を減らし、検診を活用することで予防につなげましょう。
代用音声について
食道がんで発声が難しくなった場合には、いくつかの代用音声が検討されます。
気管食道シャント法:気管と食道の間にシリコン製の一方通行弁(プロヴォックス®)を留置し、肺からの呼気を利用して発声する方法。
電気咽頭:電気式人工喉頭をのど元にあて、振動を利用して発声する方法。
食道発声法:空気を呑み込み、食道内にとどめ吐き出すことで発声する方法。いわゆるゲップによる発声
口腔・咽頭がん患者さんの在宅療養を支える訪問看護と訪問リハビリテーション
口腔・咽頭がんの治療を終えて退院された後、あるいは再発・進行によって通院が困難になった場合でも、患者さんが住み慣れたご自宅で安心して療養を続けるには、医療的かつ生活的な支援を両立できる体制が不可欠です。その中核となるのが「訪問看護」と「訪問リハビリテーション」です。
これらのサービスは、身体的苦痛の緩和、栄養・生活機能の維持、精神的支援、さらにはご家族の介護負担軽減にもつながる、在宅医療の大きな柱となります。
訪問看護の役割:術後ケア、症状緩和、栄養・心理的支援
● 症状管理と術後のケア
訪問看護師は、口腔・咽頭がんの手術後に生じやすい身体的な負担を軽減し、患者が安心して日常生活に復帰できるようにきめ細やかな支援を行います。舌や咽頭の切除後には嚥下障害や発声障害がよく見られるため、嚥下リハビリテーションや言語療法士との連携、必要に応じた経管栄養の導入などを通じて機能の安定を図ります。また、口腔内の乾燥や痛みに伴う食事困難、出血や感染のリスクに対しては、口腔ケアやスキンケアを組み合わせて対応します。
さらに、放射線治療や化学療法が行われている場合には、副作用として現れる倦怠感、食欲不振、味覚障害、口内炎、手足のしびれなどを観察し、薬剤管理を適切にサポートします。頸部リンパ節転移や肺転移に伴う疼痛や呼吸苦が出現した場合には、緩和ケアの視点から疼痛コントロールや呼吸補助を行い、快適な在宅療養環境を整えることも重要な役割です。このように訪問看護は、治療後の生活上の困難を最小限に抑え、患者が自宅で安心して療養を続けられるよう多面的な支援を担っています。
● 栄養管理と経管栄養サポート
栄養管理においては、嚥下機能の低下や口腔内の痛みによって低栄養に陥りやすい口腔・咽頭がん患者の状態を把握し、医師や管理栄養士と連携して食事形態の工夫や補助栄養食品の導入を提案します。経口摂取が難しい場合には胃ろうや経鼻経管栄養、輸液ポートによる栄養補給を用いて脱水や体重減少を予防し、治療効果を支える体力の維持を図ります。
● 精神的ケアとACP(人生会議)の支援
患者とご家族が抱える精神的な不安にも寄り添い、訪問看護師は信頼できる相談相手として心情を丁寧に傾聴します。進行期や終末期には、嚥下困難や呼吸困難、疼痛に対する不安が強まるため、安楽な体位の工夫や症状を和らげる援助を行うことに加え、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を通じて「どのように最期を迎えたいか」という本人と家族の思いを尊重した話し合いを支援します。
こうした医療的・生活的・心理的ケアを総合的に提供することで、訪問看護は口腔・咽頭がん患者の在宅療養を支える中心的な役割を果たしているのです。
訪問リハビリテーションの内容:体力維持と生活再建の支援
● 理学療法(PT)・作業療法(OT):体力・機能維持の支援、日常生活の再構築
訪問リハビリテーションにおいては、口腔・咽頭がん手術後や治療後に生じやすい筋力低下や倦怠感、体力減少に注目し、患者の身体機能を維持・回復させるための運動プログラムを構築します。特に、長期安静による廃用症候群を予防するために筋力強化訓練やバランス訓練を取り入れ、歩行や立ち上がりなど日常生活に直結する基本的動作の自立性を高めます。
また、骨転移のリスクを考慮しながら安全に行える運動を選択し、活動範囲を広げることを支援します。呼吸リハビリテーションによって呼吸筋を鍛え、全身の持久力を高め、身体への負担を軽減します。さらに、杖や歩行器などの福祉用具の選定や使い方をアドバイスし、ご自宅での安全な移動をサポートします。
その他にも、食事動作に関して嚥下しやすい姿勢や食器の使い方を練習し、必要に応じて補助具や工夫された調理法を取り入れることで、安全に食事を楽しめるようサポートします。発声や会話に困難がある場合には、筆談やコミュニケーション機器の活用方法を指導し、社会的なつながりを維持できるよう支援します。
住環境に関しては、生活動線の見直しや家具の配置換え、手すりの設置や段差解消などを提案し、安全で安心できる暮らしの場を整えます。
こうした取り組みにより、患者は身体的な制限を補いながら生活動作への自信を取り戻し、治療後も自立性を保ちながら自分らしい日常を送ることが可能となります。
● 社会参加と心理的回復の促進
さらに、在宅での療養生活における大きな心の支えとして、リハビリ専門職は患者の社会参加や趣味活動の再開を積極的に後押しします。口腔・咽頭がんの治療後は嚥下障害や発声の困難さ、外見の変化などから外出機会が減り、人との交流を避けがちになることがあります。しかし、近隣でのウォーキングや地域の体操教室への参加、絵画や園芸といった趣味活動の再開、さらにはオンラインサロンやリモート交流を通じた仲間づくりなど、患者一人ひとりの興味や体調に合わせた活動プランを提案することが可能です。
こうした「できること」を少しずつ増やしていく経験は、自尊心の回復や孤立感の軽減につながり、身体機能の回復にとどまらず心の再生を促します。リハビリは単なる機能訓練にとどまらず、生きがいを再構築するプロセスを支える重要な役割を担っているのです。
多職種連携によるチームアプローチの重要性
口腔・咽頭がんの患者さんは、身体症状だけでなく、栄養・生活機能・精神面・経済的問題など、多方面にわたる課題を抱えることがあります。こうした複雑なニーズに応えるためには、以下のようなチーム連携による対応が不可欠です。
- 医師(主治医)
- 訪問看護師
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
- 管理栄養士
- 薬剤師
- ケアマネジャー
- ソーシャルワーカー
- ホームヘルパー など
適切な情報共有を通じて、全員が一つの目標に向かって連携することが、より良い療養環境の実現に繋がります。
訪問サービス導入の流れとプラン作成
訪問看護やリハビリテーションの導入は、入院先の医療機関や地域のケアマネジャー、在宅支援チームを通じて進められます。退院前には「退院前カンファレンス」が開かれ、退院後の生活設計や支援体制が協議されることもあります。
サービス開始後には、訪問看護師やリハビリ職種が全身状態・生活状況・本人の希望を踏まえたアセスメントを行い、個別の看護計画・リハ計画を作成します。このプランは定期的に見直され、常に患者さんの状況に応じた最適な支援が提供されるよう調整されます。
大田区鵜の木の訪問看護・訪問リハビリ ─ 大田ケア訪問看護ステーション
大田ケア訪問看護ステーションでは、口腔・咽頭がんの治療後や再発・進行期にあるご利用者さまが、ご自宅で自分らしく療養生活を送ることができるように、訪問看護師とリハビリ専門職が連携して支援を行っています。
私たちの強みは、ご利用者さまのわずかな体調や食欲の変化、生活リズムの変動を丁寧に見逃さずキャッチし、必要な支援をすぐにご家族と共有できる体制を整えている点にあります。栄養管理、症状緩和、体力維持の看護・リハビリを軸に、ご家族とチームで在宅ケアを進めています。
がんの緩和ケアの土台は「対話による心のつながり」
口腔・咽頭がんのご利用者さまにとって、術後の体調変化や嚥下障害、栄養不良、そして精神的な不安は避けて通れない課題です。訪問看護師は、患者さんの体調や精神状態だけでなく、食事摂取量や嚥下の様子、体重変化、水分バランスまで細やかに観察し、必要に応じてケアプランを柔軟に調整します。
舌や咽頭の切除後には、嚥下困難、誤嚥、味覚障害、口腔乾燥といった症状への対応が求められるため、看護師がこまめに状態を把握し、医師や言語聴覚士、管理栄養士と連携しながらサポートを行います。食事形態の工夫や補助栄養食品の導入、必要に応じた経管栄養の管理なども重要な支援の一部です。
リハビリスタッフもまた、ご利用者さまの「食事を少しでも楽しみたい」「声を取り戻したい」「体力を維持したい」といった目標を実現するための支援内容を、常にご家族と共有します。その過程で、ご家族さまも「ケアチームの一員」として主体的に関わることができ、在宅療養を共に支える存在となります。
このように、医療者とご家族さまが連携することで、ご利用者さまは術後の困難を乗り越えながら、自宅でも安心して生活を続けられる環境が整えられていきます。
24時間365日対応可能な安心の連絡体制
大田ケアでは、緊急時にも対応できるよう24時間365日体制の連絡窓口を完備。たとえば、胃瘻のトラブルや急な嘔吐・下痢、脱水が懸念される場合にも、専門の看護師が迅速に受診先の案内や応急処置のアドバイスを行うことが可能です。
訪問開始時に、緊急時の対応フローを説明し、夜間や休日にも慌てず冷静に行動できるようサポートします。
ご家族さまも安心して関われるケアの仕組み
訪問スケジュールやケアプランの内容については、ご利用者さまの生活スタイルやご家族の都合を丁寧に伺いながら調整。ご家族さまが果たす役割も明確にし、「無理なく・安心して支えることができる」体制づくりを目指します。
「自分らしく、生きる」を一つひとつ増やす
口腔・咽頭がんの療養生活では、「食べること」「動くこと」「人と話すこと」が失われがちですが、大田ケアでは、そうした日常の一つひとつを大切に支えています。訪問看護と訪問リハビリが連携し、ご利用者さまの「その人らしさ」を尊重しながら、自宅で安心して過ごせる日々を創造します。
「治療が終わったけど食事に不安がある」「体力が戻らなくて外に出るのが億劫」「家族がどうサポートすればいいか分からない」──そんな時は、どうぞお気軽にご相談ください。大田ケアのチームが、一緒にその一歩を支えてまいります。
FAQ:よくある疑問にQ&A形式で回答
Q. 訪問看護サービスを利用するにはどうすればよいですか?
A. ご利用を希望される場合は、まずかかりつけ医または地域包括支援センターや居宅介護支援事業所を通じて要介護認定の申請を行ってください。要介護認定がおりた後、ケアマネジャーがケアプランを作成し、そのプランに基づいて大田ケア訪問看護ステーションがサービスを提供します。直接当ステーションにご連絡いただいても手続きの流れをご案内できますので、お気軽にお問い合わせください。
Q. 週に何回、何時間利用できますか?
A. 訪問看護の頻度や時間は、ケアプランで決定します。通常は週に1~3回、1回あたり30分から90分程度が目安ですが、症状の度合いやご家族のご希望によって柔軟に調整可能です。リハビリテーションを行う場合や症状管理が多い場合は、より頻度が増えることもあります。
Q. 料金の自己負担はいくらですか?
A. 介護保険をご利用の場合は、要介護度に応じて自己負担が原則1〜3割となります。医療保険適用の訪問看護では、医師の指示で行う注射や点滴なども保険診療としてカウントされ、ご負担額は医療保険の自己負担割合に準じます。詳しい費用については、個別性があるのですが、1割負担の方で60分訪問1000円ぐらいと考えておくとわかりやすいです。
Q. 24時間対応は可能ですか?
A. 大田ケアでは夜間・休日のオンコール体制を整えており、急な痛みの悪化や呼吸困難などの緊急事態にも電話でのご相談を受け付けています。緊急度が高いと判断した場合は、訪問看護師が緊急訪問を行い、一次的な対応を実施します。
Q. 訪問リハビリテーションはどのような内容ですか?
A. がん治療に伴う筋力低下や関節可動域制限、呼吸機能の低下を軽減するための運動プログラムを提供します。ベッド上で行う抗重力運動や呼吸リハビリ、リンパ浮腫ケアを組み合わせ、患者さんの体調に合わせて無理なく継続できる方法をご提案します。
Q. 自宅に必要な福祉用具はどう手配すればよいですか?
A. ケアマネジャーと連携し、手すりやスロープ、ポータブルトイレ、シャワーチェアなどの福祉用具を介護保険サービスでレンタルできます。大田ケアのスタッフがご自宅を訪問して適切な配置や使い方をアドバイスし、安心・安全な環境づくりをサポートします。
Q. 医師との連携はどのように行われますか?
A. 訪問看護師は定期的にバイタルサインを記録し、症状の変化を詳細に把握して医師に報告します。必要に応じて医師の指示を取り付け、薬剤の調整や注射管理を行うほか、電話やオンラインでの迅速な連絡体制を整えています。
Q. 心理的なサポートも受けられますか?
A. 看護師が日常的な会話を通じて不安や悩みを傾聴します。ご家族へのサポートも重視し、介護負担や経済的な不安についても適切な制度やサービスを紹介します。
Q. アドバンス・ケア・プランニング(ACP)はどのように進めますか?
A. ACPでは、医師が予後予測を説明し、延命治療の希望や最期の過ごし方について患者さんの意思を整理します。大田ケアのチームもその意思が尊重されるようサポートします。
Q. 申し込み後、どのくらいで訪問が始まりますか?
A. ケアプランが確定し、必要書類が整い次第、通常は1週間以内に初回訪問を設定します。急ぎの場合は調整してより早い開始も可能ですので、ご希望があればご相談ください。
情報源・出典元データなど
専門機関
- 世界保健機関(WHO)palliative care fact sheet
- 国立がん研究センター がん情報サービス「緩和ケア」
- 咽頭(いんとう)がん | 国立がん研究センター 東病院
- 日本緩和医療学会 ガイドラインページ
- 厚生労働省「緩和ケアの推進」ページ/第4期がん対策推進基本計画
- NCCN Guidelines® Palliative Care(2024年版)
- 公益財団法人 日本訪問看護財団
学術論文
- アドバンス・ケア・プランニング(ACP)に関する看護研究(J-STAGE)
- Patient-Controlled Analgesia in Palliative Care: Exploratory Scoping Review(2025)
- 在宅ホスピスにおける家族介護者の負担研究(J-HOPE)
- Mindfulness in End-of-Life Care(2024, Sciencedirect)
- Resilience-Building in Palliative-Care Professionals: Scoping Review(BMJ Supportive & Palliative Care 2025)
その他、Webサイト
大田ケアに相談する、知る
■看護・リハビリスタッフによる個別相談(無料)を予約する
https://otacare.com/otoiawase/
*お問合せフォームに、「個別相談希望」とご記載ください。折り返しご対応させていただきます
■大田ケアのパンフレットを見る
https://otacare.com/news/20250412/
☐私たちと一緒に働きませんか?採用情報を確認する
https://otacare.com/rikuru-to/
*看護・リハビリスタッフともに積極的に受け付けております
☐スタッフインタビューを見る
https://otacare.com/team/