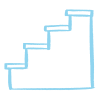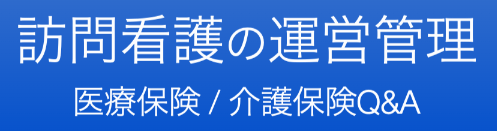パーキンソン病は、脳内ドパミンの減少によって「手足のふるえ」「動作の緩慢」「姿勢の不安定」などの運動症状が進行する神経変性疾患で、在宅生活では日常動作の負担が大きくなりやすい病気です。そのため、自宅で安心して暮らし続けるためには、症状変化に応じた医学的ケアを行う訪問看護と、身体機能の維持・転倒予防・生活動作の改善を目的とした訪問リハビリの併用が重要になります。本記事では、パーキンソン病の基礎知識から、自宅でできるケア、訪問サービスの具体的な役割まで分かりやすく解説します。
Contents
神経変性疾患であるパーキンソン病
パーキンソン病(Parkinson’s disease; PD)は、中脳黒質にあるドパミン産生神経細胞が徐々に変性・脱落することで、運動制御に重要な黒質―線条体回路が障害されて発症する進行性の神経変性疾患です。病理学的には、変性した神経細胞内にα‐シヌクレインからなるレビー小体が認められることが特徴で、これが運動症状のみならず認知機能や自律神経機能にも影響を及ぼします。
パーキンソン病有病率と患者数の動向
最新の「令和5年(2023)患者調査」によると、パーキンソン病を含む脳血管疾患以外の神経系疾患の受療率は高齢化とともに増加傾向にあり、特に75歳以上の高齢者での受療率が高くなっています。詳細な都道府県別・年齢階級別の患者数は、厚生労働省の統計サイトで公開されており、地域差や性別差の分析が可能です。
パーキンソン病の代表的な運動症状と非運動症状
運動症状の四大徴候
・振戦(振え):PDでは安静時に4〜6Hzの規則的な振戦が片側優位に生じます。
・筋強剛(固縮):「歯車様固縮」と呼ばれる関節を動かす際のカクカクとした抵抗。
・無動・寡動(ブレイディキネジア):動作の開始・継続が遅れ、歩行では小歩・すり足になります。
・姿勢反射障害:転倒しやすく、バランス保持が困難になります
非運動症状の多様性
非運動症状は診断前から出現しやすく、以下のようなものがあります
・嗅覚低下:発症前の段階で約70〜90%にみられるとされる重要な前兆。
・睡眠障害:レム睡眠行動異常(RBD)や不眠。
・自律神経症状:便秘、起立性低血圧、排尿障害など。
・精神・認知症状:うつ、認知機能低下、精神病症状も経過中に現れ得ます
予後と長期的管理のポイント
パーキンソン病は進行性疾患のため継続的な治療・ケアが必要です。定期的な神経内科受診で薬剤調整を行い、リハビリテーションを継続することで生活の質(QOL)を維持・向上させます。また、指定難病医療費助成や介護保険サービスを活用し、患者さんやご家族の経済的・心理的負担を軽減することも重要です。詳細な支援制度はお住まいの自治体にお問い合わせください(こちらは大田区のホームページです)。
初期症状チェックの特徴と早期発見のポイント
歩く時に足を引きずったり、腕を振らない歩き方、歯磨きや洗髪が難しくなったりといった日常生活における違和感、じっとしている時に震えが起こるといったものがあれば、パーキンソン病が一つの可能性として考えられます。特に、パーキンソン病の初期症状として、安静時の震え(安静時振戦)が多くみられます。
安静時振戦と動作時振戦の見分け方
パーキンソン病を特徴づける「振戦」は、何も動かしていないときに手足が小刻みに震える安静時振戦が代表的です。一方で、薬剤性パーキンソニズムでは動作時の振戦が多く、左右対称に出現する傾向があります。
「安静時振戦」、これは何も動かしていない状態、例えば椅子に座っているときや手を机の上に置いているときなどに、4~6Hz程度の比較的規則的な小刻みな震えが生じるものです。自分の意志で動かそうとすると振戦は一時的に抑制され、通常は身体の片側(手指、手首など)から始まって、やがてもう一方へと広がっていきます。
動作時振戦(動作振戦・保持振戦)は、腕を前に伸ばす・物をつかむなどの意図的な動作や姿勢を保持している最中に見られる振戦です。薬剤性パーキンソニズムでは特にこの動作時振戦が目立ち、振戦の出現が左右対称であることが多いのが特徴です。抗精神病薬や一部の消化管運動調整薬などが原因となり、薬剤の服用中止後も持続する場合があるため、薬歴の確認とともに振戦の出現タイミングや左右差の有無をしっかり観察することが鑑別のポイントとなります。
- 安静時振戦:休息時に4~6Hz程度の規則的な震え
- 動作時振戦:物をつかもうとしたときなど、動作中に震える
無動・寡動のサインと筆記動作の変化
動き全体が遅くなる無動・寡動は、歩幅の減少や腕振りの低下、「仮面様顔貌」と呼ばれる表情の乏しさにもつながります。
パーキンソン病のもう一つの大きな運動症状である無動(ブレイディキネジア)・寡動は、身体全体の動作が遅く、小さくなる状態を指します。歩行時には一歩一歩の歩幅が狭まり、腕の振りが減少(片側から始まることが多い)、「すり足」あるいは「すくみ足」と呼ばれるすくみ現象が現れやすくなります。また、表情筋の動きが低下して「仮面様顔貌(マスク顔貌)」と呼ばれる無表情が生じ、会話時の表情変化が乏しくなるのも特徴の一つです。
筆記動作の観察は、早期発見に有用な小字症(マイクログラフィア)のサインを捉える手がかりとなります。連続した文字列の書字よりも、文章全体を書こうとした際に文字の大きさが急激に小さくなる傾向があり、その縮小率は健常者に比べて有意に大きいことが報告されています。
たとえば「た」を10回連続で書く場合と、10文字程度の文章を書く場合を比較すると、パーキンソン病患者は後者でより顕著に文字が小さくなることが知られています。日常生活では、メモを取る・家計簿をつけるなどの筆記作業中に文字が小さくなる・書きづらくなるといった変化に気づいたら、神経内科での検査を検討すると良いでしょう。
※早期発見には、ご家族や介護者による日常動作の観察が有効です
パーキンソン病の初期症状疑いがあるときは神経内科へ
早期の専門診療で的確な診断と治療開始が可能となり、進行抑制やQOL維持に大きく寄与します。
早期発見のメリット
- 薬物療法の最適化:L-dopa製剤やドパミンアゴニストは、症状の軽い段階で開始すると「ウェアリングオフ」やジスキネジアの発現を抑えながら効果を長持ちさせやすい。
- リハビリプランの早期立案:運動機能低下を最小限に抑える個別プログラムを発症直後から組むことで、転倒リスク軽減や日常動作維持につながる。
- 精神・非運動症状への対応:便秘、睡眠障害、うつ気分など非運動症状は「運動症状の前ぶれ」として現れることもあり、総合的なケアが必要です。
受診前に押さえておきたい初期症状チェックリスト
振戦以外の初期症状
無動・寡動(ブレイディキネジア):動作全般の緩慢化、歩幅減少、仮面様顔貌
小字症(マイクログラフィア):筆記時に文字が急激に小さくなる変化をセルフチェック
非運動症状:早期から便秘、嗅覚低下、うつ症状が出ることもある。
ご家族・介護者の観察ポイント
左右差の確認:症状が片側優位かどうかをメモ
日常動作の変化:立ち上がり、歩行、階段昇降の所要時間や動作のぎこちなさ
振戦のタイミング:安静時 vs 動作時(薬剤性パーキンソニズムでは動作時振戦が左右対称に出やすい)
持参すると便利な情報・資料
服用中の薬リスト:向精神薬、制吐薬、胃腸薬などパーキンソニズムを誘発し得る薬剤を含む全薬剤名
症状記録表:振戦・無動・便秘・睡眠などを1週間程度まとめたメモ
家族歴・既往歴:パーキンソン家系、若年発症例の有無
パーキンソン病の初期症状は見逃されやすいため、少しでも「手指の振え」「動作の鈍さ」「筆記の変化」を感じたら、早めに神経内科を受診しましょう。公的臨床ガイドラインに準拠した専門的な診断と治療が、その後のQOL維持に直結します。
リハビリテーションでQOLを維持するコツ
理学療法(PT):バランス訓練、歩行訓練で転倒予防
バランス訓練や筋力強化運動を定期的に行うことで、姿勢反射障害による転倒リスクを軽減します。パーキンソン病では筋固縮や無動・寡動、姿勢反射障害のために転倒リスクが高まります。薬物療法で運動症状がある程度改善しても、バランス能力や歩行パターンは残存しやすいため、理学療法(PT)による専門的介入が不可欠です
- トレッドミル併用歩行:一定速度のトレッドミル上を歩くことで歩幅の拡大やリズム改善を促します。トレッドミル+視覚的・聴覚的キューイング(メトロノームや床にライン)を組み合わせると、歩行速度やストライド長が有意に向上することが報告されています。
- 突進現象(フォルスティッピング)対策:歩行速度が突然上がる現象には、視覚的目印で歩幅を制御する訓練や、音響キューによるリズム維持訓練が有効です。
- 階段昇降訓練:手すりを使った昇降動作を反復し、足部・体幹の協調性を改善。
作業療法(OT):日常生活動作(ADL)の維持・改善を目的とした訓練
OTは、患者さんが「日常生活をいかに自立的に送るか」を追求する領域で、パーキンソン病では特にADL維持・改善が中心となります。日常動作や環境調整を通じてQOL向上を図り、公的支援と連携した介入が求められます。
- 食事:滑り止めマットや吸盤つき食器で安定性を向上。スプーン・フォークのグリップを太く加工し、手指の硬さを補助。
- 整容・更衣:長い靴下用ストッパー、着脱しやすい前開き衣類の選定。座位での更衣動作の段階分割指導(片側ずつ腕を通す、片足ずつズボンを上げる)。
- 排泄・入浴動作:トイレの手すりの最適な設置位置を測定し、立ち座り動作が滑らかになるようシミュレーション。入浴時、浴槽の跨ぎ動作訓練、滑り止めステッパーを用いた安全動作、シャワーチェアの活用指導。
- 書字・コミュニケーション動作・小字症(マイクログラフィア)対策:大きなマス目のノートやペン先に視覚的ガイドラインを付与。
- パソコン利用支援:キーボードカバーで補助し、誤入力を軽減。
- 住環境調整:段差解消や家具配置の最適化、照明改善で転倒リスクを低減。
- 家族・介護者向け指導:正しい補助方法、コミュニケーションのタイミング、サポートの切り替えポイントを共有し、過剰介助を防止。
言語療法(ST):構音訓練、嚥下訓練で誤嚥性肺炎予防
パーキンソン病では構音障害や嚥下障害が高頻度にみられ、自覚が乏しい中で誤嚥性肺炎のリスクが増大します。ST(言語聴覚療法)では、発声・嚥下機能の評価から個別プログラムを策定し、合併症予防を目指します。
- 問診・スクリーニング:異物感、むせ、体重減少などの徴候を確認。パーキンソン病患者では不顕性誤嚥が多いため、自覚がなくてもスクリーニングを推奨します。
- 嚥下訓練プログラム:発声訓練で嚥下機能を維持し、誤嚥性肺炎予防にも効果的です。嚥下機能を支える咽頭・喉頭周囲の筋力と協調性を高める体操的訓練と、実際の飲み込み動作を安全に行うための摂食姿勢・戦略、さらに食べ物や飲み物の特性を調整する食形態の工夫、そして味覚や触覚を活用して咽頭感覚を再教育する認知―嚥下統合訓練から構成されます。
日常生活を快適にする環境整備と工夫
薬の“オン”タイム管理:外出やリハビリは薬効ピーク時にスケジュール
薬の“オン”タイム管理では、外出やリハビリなどの活動を薬効がピークに達する時間帯に合わせて計画することが重要です。
たとえば、主要な運動症状を緩和するレボドパ製剤は、服用後約30分~1時間で最高血中濃度に達し、その後徐々に効果が低下していきます。したがって、通院や買い物、理学療法(PT)などの運動訓練をこの“オン”タイムの間に組み込むことで、最もスムーズに動ける状態を活かせます。実際、鳥取医療センターのガイドラインでは、「薬効時間を見極めながらリハビリを行うことで、体を動かした際の効果が最大化される」と明記されています。
また、内服スケジュールを手帳や専用アプリで可視化し、認知機能の低下に備えたダブルチェック(本人と介護者による確認)を併用すると、飲み忘れや重複投与のリスクを低減できることが徳島病院の研究で示されています
家庭内の危険箇所対策:滑り止めマットや手すり設置で転倒予防
家庭内の危険箇所対策としては、滑りやすい床材の除去と手すりの設置が基本です。特に廊下・浴室・トイレなど水濡れや段差のある場所には、滑り止めマットを敷いて床と固定し、足元の不意なずれを防ぎます。加えて、立ち座りや移動動作を補助するために、壁面や階段には高さ・太さの調整された手すりを設置します。
埼玉労働局の安全衛生資料でも、滑り止めマットの固定や段差への目印付与が「転倒災害の防止に有効」として推奨されており、家庭内においても同様の効果が期待できます
食事・便秘対策:高タンパク・高食物繊維食を心がけ、慢性便秘を軽減
食事・便秘対策では、高タンパク・高食物繊維食を心がけ、水分摂取も十分に行うことが便秘の軽減につながります。パーキンソン病患者では腸の蠕動運動が低下しやすく、発症前から便秘症を抱える例も少なくありません。
最新の慢性便秘症診療ガイドライン2023では、食物繊維を豊富に含む全粒穀物や豆類、野菜を積極的に摂取し、加えて1日1.5~2リットルの水分をこまめに補うことが推奨されています。
また、たんぱく質は筋肉量維持の要であると同時に、運動機能の低下を抑制する「食べる薬」として重要視されており、肉・魚・大豆製品などを1食あたり20~30gずつ摂取することで、リハビリ効果の向上も期待できます
ストレスケア:軽い有酸素運動や趣味活動で気分を安定化。
ストレスケアには、軽い有酸素運動と趣味活動を組み合わせることが有効です。有酸素運動(ウォーキングや自転車こぎなど)を週3回、1回30分程度実施すると、脳内の神経可塑性が促進され、運動のみならず情動や認知機能の改善にも寄与することが報告されています。
さらに、自分の好きな趣味や創作活動を定期的に行うことで、気分転換と社会的交流の機会が増え、慢性的なストレスホルモン(コルチゾール)の上昇を抑制できます。日常の習慣に組み込む際には、小さな目標を設定し達成を祝うことで、継続しやすい環境を作ることがポイントです。これらのストレスケアは、パーキンソン病の進行抑制だけでなく、QOL(生活の質)の維持にも直結します。
指定難病制度を活用した医療費助成
医療費助成の対象条件と申請の流れ
パーキンソン病は「指定難病6」に該当し、診断基準を満たせば以下の助成が受けられます。
- 重症度分類による認定
- 軽症でも月額医療費33,330円超が年間3月以上ある場合の「軽症高額該当」扱い。
申請には「臨床調査個人票」と必要書類を居住自治体に提出し、審査後に「医療受給者証」が交付されます。認定は原則1年ごとで、更新申請が必要です。
大田ケア訪問看護ステーションにおけるパーキンソン病患者さん支援
大田ケア訪問看護ステーションのサービス提供エリアと専門スタッフ
大田ケア訪問看護ステーションでは、大田区を中心に、世田谷区・目黒区・品川区・川崎市一部エリアまでを対象に在宅でのパーキンソン病患者支援を行っています。看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が協力し、身体機能の維持・向上、日常生活動作の自立支援、誤嚥性肺炎予防といった課題に対して包括的なプログラムを実践しています。
訪問リハビリテーションのメリット
パーキンソン病患者にとって、訪問リハビリテーションは病院外の環境で日常生活動作(ADL)に即した訓練を継続できる点で大きな意義を持ちます。特に大田ケアでは、パーキンソン病治療ガイドラインに基づき、バランス能力の改善や歩行速度向上に効果的とされる訓練やリズム運動を取り入れたエアロビック訓練など多彩なアプローチを組み合わせ、週2~3回の訪問リハビリと自主トレーニングを組み合わせる形でプログラムを設計しています。これにより、筋力低下や姿勢反射障害による転倒リスクを抑えつつ、日常生活での動作をより安全・快適に保つことが可能となります。
リハビリテーションでは、歩行や姿勢の改善を目指して、科学的かつ創意工夫に富んだ方法が取り入れられています。そのひとつが「リズムトレーニング」。たとえば、床に引かれたラインに沿って歩く訓練や、メトロノームの一定のテンポに合わせて歩幅を保つ練習などです。こうした工夫は、パーキンソン病などで見られる突進現象やすり足といった運動障害の改善に役立ち、動作の自動化を促す効果が期待されています。さらに、このようなリズムに着目した介入は、在宅での長期リハビリにおいても有効性が報告されており、ご本人の継続意欲を高める一助にもなっています。リズムに乗って歩くことで、自信や楽しさが生まれます。
食事、嚥下機能ケアと言語聴覚士の役割
一方、「食べる」機能の維持もまた、生活の質を左右する大切な要素です。言語聴覚士(ST)は嚥下機能の評価を通して、飲み込みの状態を細やかに観察します。誤嚥を防ぐためには、口腔ケアやアイスマッサージなどのケアが不可欠です。覚醒が良好な時間帯には、介助者とのコミュニケーションや発声練習、さらには歌唱といった活動も積極的に取り入れられ、機能の維持に繋げています。なお、STの評価は月に1回が基本となるため、日常の観察やケアのポイントは看護師へしっかりと引き継がれ、チームで支える体制が整えられています。
訪問看護師の薬剤管理とオン/オフタイム調整
また、訪問看護師は薬剤管理や全身状態の観察を通じ、リハビリの効果を最大化できるよう助言します。特にレボドパ製剤などの「オン/オフ」タイムを把握し、外出やリハビリを薬効ピーク時にスケジュールすることで、運動機能を最も発揮しやすいタイミングを逃しません。内服スケジュールは手帳等で可視化し、飲み忘れ防止のために本人と介護者によるダブルチェック体制を構築します。
24時間体制の安心サポート
大田ケア訪問看護ステーションのサービスは、土日対応・24時間オンコール体制のもと提供され、急な体調変化にも看護師が即時対応できる体制を整えています。一人ひとりのニーズや生活リズムを大切にしながら、専門家チームが連携して在宅生活を総合的にサポートする大田ケア訪問看護ステーションの取り組みは、パーキンソン病患者とそのご家族が安心して暮らし、よりよい日常を送るための大きな支えとなっています。
■看護・リハビリスタッフによる個別相談(無料)を予約する
https://otacare.com/otoiawase/
*お問合せフォームに、「個別相談希望」とご記載ください。折り返しご対応させていただきます
■大田ケアのパンフレットを見る
https://otacare.com/news/20250412/
☐私たちと一緒に働きませんか?採用情報を確認する
https://otacare.com/rikuru-to/
*看護・リハビリスタッフともに積極的に受け付けております
☐スタッフインタビューを見る
https://otacare.com/team/
FAQ:よくある疑問にQ&A形式で回答
Q. 根治は可能?
A. 現在は根治療法がなく、症状緩和と進行抑制が治療目標です。
Q. 受診すべき専門医は?
A. 神経内科または難病医療指定医療機関を受診してください。
情報源・出典元データなど
専門機関
- パーキンソン病診療ガイドライン2018
- 難病情報センター
- 指定難病患者への医療費助成制度のご案内
- パーキンソン病│厚生労働省
- 指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1~341)│厚生労働省
- パーキンソン病治療の最先端 持続的な注射ができる薬と機器の導入 | 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター National Center of Neurology and Psychiatry
- パーキンソン病とパーキンソン症候群:「パーキンソン病らしさ」とは? | 国立長寿医療研究センター
- パーキンソン病センター | 独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター
学術論文
- パーキンソン病患者の服薬指導
- パーキンソン病のリハビリテーション治療
- パーキンソン病の認知機能低下が入院リハビリテーション効果に及ぼす影響と有酸素運動の効果についての検討
- パーキンソン病の栄養療法の確立に向けて
- パーキンソン病における便秘症
- 患者の転倒リスクと予防対策の組み合わせ方とその効果に関する文献検討
- パーキンソン病患者における便秘に対するラクツロースの効果:探索的パイロット研究【JST機械翻訳】
- パーキンソン病患者の気分および認知障害に対する高圧酸素療法の影響【JST・京大機械翻訳】
- パーキンソン病患者の便秘改善に対する取り組み~便秘体操と腹部マッサージによる効果の検討~
- パーキンソン病の基礎知識と嚥下障害患者の栄養管理
- パーキンソン病―看護の視点~心や身体のケアについて
- パーキンソン病患者に対する心理的アプローチの取組み
その他、Webサイト
大田ケア訪問看護ステーションは、大田区鵜の木にあるステーションです。看護・リハビリともに土日営業を行っています。大田区を中心に、世田谷区、目黒区、品川区、川崎市の一部に訪問しております。
■看護・リハビリスタッフによる個別相談(無料)を予約する
https://otacare.com/otoiawase/
*お問合せフォームに、「個別相談希望」とご記載ください。折り返しご対応させていただきます
■大田ケアのパンフレットを見る
https://otacare.com/news/20250412/
☐私たちと一緒に働きませんか?採用情報を確認する
https://otacare.com/rikuru-to/
*看護・リハビリスタッフともに積極的に受け付けております
☐スタッフインタビューを見る
https://otacare.com/team/
大田ケアのコンテンツが、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
大田ケア訪問看護ステーション
info@otacare.com