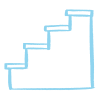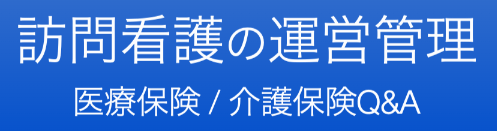Contents
大田区で進む「認知症の地域包括ケア」とは
地域包括ケアの基本理念
「地域包括ケアシステム」とは、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるように支援する仕組みを指します。
これは単なる介護サービスの集まりではなく、「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」という5つの要素を地域単位でつなぐネットワーク構想です。
厚生労働省が2014年に提唱して以来、全国の自治体で整備が進み、大田区でも「地域包括支援センター」を核に、行政・医療機関・介護事業所・住民団体が連携する形で進化してきました。
この中でも特に重要なのが、「認知症にやさしい地域づくり」。大田区では、認知症を「支える」だけでなく、「共に生きる」社会を実現するための地域包括ケアの深化が進められています。
大田区の高齢化と認知症の現状
大田区の総人口は約74万人(2025年時点)。そのうち高齢化率は25%を超え、4人に1人が高齢者という状況です。
推計によると、認知症高齢者は約2万人前後にのぼり、軽度認知障害(MCI)を含めればさらに多くの人が支援を必要としています。
一方で、介護保険サービスだけでなく、地域での見守り・相談・交流など、「制度の外側」にある支援の重要性も高まっています。
特に単身高齢者や認知症独居世帯の増加が顕著であり、地域包括ケアは「家庭内の支え」から「地域全体での支え」へと変化を迫られています。
認知症の地域包括ケアが目指すもの
大田区が掲げる認知症施策の柱は次の3つです。
- 早期発見・早期支援の体制づくり: 認知症初期集中支援チームの強化、医療機関連携の促進
- 家族・地域・専門職の協働ネットワーク構築: 地域ケア会議や認知症カフェを通じた情報共有
- 本人・家族の「生活の質(QOL)」向上: 精神的サポートや社会参加の機会の創出
これらの取り組みは、「介護の効率化」ではなく、「人の暮らしを中心に据える支援」へと軸足を移したものです。
介護負担軽減のための地域包括支援の仕組み
家族介護者の現実
認知症の介護を担う家族は、身体的にも精神的にも大きな負担を抱えています。
大田区が実施した高齢者実態調査によると、介護を担う家族の約7割が「ストレスを感じている」と回答しています。介護時間が長く、仕事や自分の生活を犠牲にしているケースも少なくありません。
「ついイライラしてしまう」「もっと優しくしたいのにできない」——そんな声は、地域包括支援センターの相談窓口で毎日のように聞かれます。この現実を前提に、地域は“介護する人を支える”体制をどう整えるかが問われています。
大田区の介護負担軽減策
大田区では、介護負担軽減を目的とした多様な取り組みが行われています。
1. 家族介護者教室・認知症家族会
区内各地域包括支援センターでは、介護家族教室や家族会を開催しています。
専門職による講座だけでなく、家族同士の交流を通じて「自分だけじゃない」と思える時間を提供。
孤立しがちな介護者の精神的サポートとしても機能しています。
2. レスパイト(介護者休養)サービス
介護者が一時的に休息を取れるよう、ショートステイや通所サービスの利用支援というものもあります。
「罪悪感なく休む」ことを支援するため、ケアマネが積極的に休養支援計画を提案する事例も増えています。
ケアマネの視点:「支援の分岐点」はどこにあるか
介護現場では、「いつどのタイミングで支援を強化すべきか」が重要です。ケアマネジャーの多くは、“家庭の限界ライン”をいかに早く見抜くかに注力しています。
- 介護者の睡眠時間が短くなっている
- 利用サービスが限界まで達している
- 家族が感情的になっている
これらは支援の転換点のサインです。地域包括支援センターとケアマネが連携し、早期に各種在宅支援サービスや家族教室、レスパイト等を提案することで、虐待や介護放棄の未然防止にもつながります。
地域で「利用できるサービス」を徹底解説
医療・介護・福祉が連携する「地域包括ケアの全体像」
認知症ケアでは、単一のサービスではなく、多職種連携が鍵になります。
たとえば、診断後の支援では以下のような流れが一般的です。
- かかりつけ医による診断・情報共有
- 地域包括支援センターでの相談・支援方針の整理
- ケアマネジャーが介護保険サービスを調整
- 通所介護・訪問介護・医療との連携支援
- 認知症カフェや地域交流による社会的支援
このように、医療・介護・地域が「顔の見える関係」で支えることで、当事者も家族も孤立しない環境をつくります。
認知症初期集中支援チーム
大田区では、認知症の早期支援体制として「認知症初期集中支援チーム」を設置。
医師・看護師・社会福祉士などの専門職が家庭を訪問し、本人・家族への支援計画を立案します。
このチームの目的は、「早期に診断・介入し、生活の混乱を最小限にする」こと。
支援後は地域包括支援センターと連携し、継続的なフォローアップを実施します。
介護負担軽減にもつながる、「早めの一手」の仕組みです。
通所介護・訪問介護・小規模多機能型の違いと選び方
認知症ケアでは、「どのサービスを使えばよいか」が大きな悩みです。
ここで代表的な3つを整理します。
| サービス名 | 特徴 | 向いているケース |
| 通所介護(デイサービス) | 送迎付きで日中の活動支援・入浴・リハビリなどを実施 | 家族が日中働いている、本人の社会交流を増やしたい |
| 訪問介護(ホームヘルプ) | 自宅での入浴・掃除・調理などをサポート | 自宅での生活維持を重視したい |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・泊まり・訪問を一体的に提供 | 介護度が上がっても住み慣れた地域で暮らしたい |
ケアマネが本人・家族の生活リズムや希望を踏まえ、複数のサービスを柔軟に組み合わせることで、介護負担を大きく減らすことができます。
サービスを上手に使うための3つのコツ
- 「できないこと」ではなく「続けたいこと」から考える: 介護プランは「支援」ではなく「生活の再設計」。本人の希望を中心に。
- 地域包括支援センターに早めに相談: 申請や手続き前でも相談OK。家族だけで悩まない。
- 認知症カフェなど“つながりの場”を活用: サービスだけでは埋まらない孤立感を、地域のつながりで補う。
認知症の地域包括ケアは、「サービスを使うこと」ではなく「暮らしを支えること」。
介護負担軽減は、制度や仕組みの話に留まらず、「人のつながり」をどう維持するかという地域全体の課題です。そして大田区は今、行政・専門職・住民が一体となってその答えを模索しています。
認知症カフェと地域交流の力
認知症カフェとは?
「認知症カフェ」とは、認知症の本人や家族、地域住民、専門職などが気軽に集い、交流・情報交換を行う場です。
コーヒーを飲みながらリラックスできる雰囲気の中で、介護の悩みや生活の不安を語り合うことができます。
その原型はオランダの「アルツハイマーカフェ」にあり、日本では2012年頃から各地で広まりました。
大田区でも区内各地で数十か所の認知症カフェが運営されており、地域包括支援センターや医療機関、ボランティア団体が中心となって開催しています。
なぜ「カフェ」なのか?
「カフェ」という形式には、2つの意味があります。
- 敷居を下げる: 福祉相談所ではなくカフェであることで、「支援を受ける側」ではなく「参加する仲間」として自然に関われる。
- 共感の場をつくる: 介護する人、支援する人、支えられる人が混ざることで、「立場を越えたつながり」が生まれる。
カフェは“情報提供の場”であると同時に、孤立を防ぐ社会的インフラでもあります。
大田区内の認知症カフェ事例
🌸 事例1:オレンジカフェ大森(地域包括支援センター大森東)
毎月第2木曜に開催されるこのカフェでは、看護師・介護支援専門員・地域住民が同席。
「家族が外出を嫌がる」「通所を拒否する」といったリアルな相談が交わされます。
ときには区の職員が制度の最新情報を案内することもあり、「生活支援と情報共有のハイブリッド」が特徴です。
🌼 事例2:みなみ六郷カフェ(民生委員・ボランティア主催)
地域住民が主導し、認知症当事者もスタッフとして参加するカフェ。
「支援される人」から「地域を支える一員」へという意識変化が生まれています。
ケアマネ・包括職員が関わる意義
カフェを運営する中で、ケアマネや包括職員が得るものも多くあります。
- サービス利用前の潜在的な相談者との接点を持てる
- 地域の「顔の見える関係」を築ける
- 本人や家族の“生活の質”を定性的に把握できる
認知症カフェは、制度外の「ソフトな支援ネットワーク」を可視化する場であり、地域包括ケアの実践の縮図でもあるのです。
地域包括支援センターの活用法
地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターは、高齢者支援の総合相談窓口です。
「介護」「医療」「福祉」「権利擁護」など幅広い領域を横断的に扱い、介護保険の申請から生活相談、虐待防止まで担います。
大田区では現在、区内に23か所のセンターが設置され、各圏域ごとに高齢者の生活を支えています。
センターの3つの柱
- 総合相談・支援業務: 介護保険申請、介護負担軽減策、医療・福祉連携、家族の悩み相談などをワンストップで対応。
- 権利擁護業務: 虐待・消費者被害・成年後見制度利用支援など、高齢者の権利を守る役割。
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務: ケアマネジャーを支援し、地域全体の支援品質を底上げする機能。(例:事例検討会・地域ケア会議の開催など)
大田区の地域包括支援センターの特徴
大田区の包括センターは、行政と医療・福祉機関の中間に立つ調整役として機能しています。
区独自の取り組みとして、「地域包括支援センター間の横断的連携」があります。
たとえば、認知症や虐待対応などセンシティブなケースは、センター同士で情報共有し、“孤立しない包括支援”を実現しています。
また、各センターが「地域ケア会議」を定期開催し、地域課題を共有・可視化する仕組みも整っています。
実際の相談事例:ある家族のケース
「母の物忘れが進んできたが、病院に行きたがらない」
「介護保険を使うほどではないと思っている」
このような“グレーゾーン”の相談は非常に多く見られます。地域包括支援センターでは、こうした段階から支援を開始し、必要に応じて認知症初期集中支援チームや医療機関と連携します。
つまり、「まだ制度利用していない人」こそ、早めに相談すべきなのです。
よくある質問Q&A
Q1. 介護保険を使っていなくても相談できる?
もちろん可能です。むしろ早期相談が負担軽減につながります。
Q2. 家族が遠方に住んでいる場合でも相談できる?
可能です。遠距離介護の調整や連絡体制づくりを一緒に考えます。
Q3. 認知症カフェや家族会の情報も教えてもらえる?
各センターで地域イベントの情報も管理しています。ぜひ活用を。
精神的サポートの重要性と実践方法
「介護うつ」を防ぐには
介護の長期化に伴い、家族が精神的に疲弊する「介護うつ」が社会問題になっています。特に認知症介護では、「感謝されにくい」「成果が見えにくい」という特性があり、心の消耗が大きいのです。
家族・本人双方への支援
精神的サポートは家族だけでなく、認知症本人にも必要です。
認知症の初期には「自分ができなくなる」恐怖や不安を感じる人が多く、孤立や抑うつにつながりやすい傾向があります。
支援の基本は、「できることを続ける」「役割を持ち続ける」こと。
地域活動・ボランティア・カフェでのスタッフ参加など、社会参加の継続が最大の精神的支援になります。
ケアマネ・専門職ができる“心の支援”
ケアマネジャーが精神的サポートを行う際に意識すべき3点があります。
- 「できていること」に焦点を当てる: 本人の失敗を指摘するより、「これができているね」と肯定的に伝える。
- 家族の罪悪感を軽減する: 「休んでもいい」「助けを求めてもいい」と言葉で示す。
- 支援ネットワークを可視化する: 誰がどこで支えているのかを図示し、「一人ではない」と実感してもらう。
心理的支援の新しい形:オンラインと地域の融合
近年はオンラインを活用した心理支援も進んでいます。
Zoomによる家族会や、LINE相談窓口など、対面とデジタルのハイブリッド支援が広がりつつあります。
地域での取り組みと今後の展望
民間と行政の協働事例
🏥 医療法人×包括支援センター連携
認知症の診断を受けた高齢者が病院退院後すぐ地域で支援につながるよう、医療・介護連携のプロトコルを策定。
「情報の断絶」を防ぐ取り組みとして注目されています。
🏘️ 商店街×ボランティア連携
商店街の店員が「認知症サポーター」として研修を受け、買い物支援や見守りを行う事例も増加中。
「地域包括ケア=特別な人の活動」ではなく、誰もが支える地域文化へと変わりつつあります。
今後の課題と展望
- 若年性認知症への対応: 就労支援や社会的孤立の防止が課題。企業連携が今後の鍵。
- ICTの活用: デジタル見守り・AIによるリスク予測など、新技術をどう地域に根づかせるか。
- 多文化共生と認知症支援: 大田区には外国籍住民も多く、言語・文化の壁を超えた支援モデルが求められています。
まとめ:大田区で安心して暮らすために
今日からできる3つの行動
- 地域包括支援センターに相談してみる: 小さな心配でも大丈夫。早めの相談が安心につながります。
- 認知症カフェに参加してみる: 支援者でも家族でも、誰でも参加可能。地域のつながりを体感できます。
- 「できること」を一つ増やしてみる: 買い物同行、声かけ、ボランティア——その一歩が地域包括ケアの一部です。
家族・地域・専門職が協働する未来へ
認知症ケアは「誰かが支える」ものではなく、「みんなで支える」時代へ。
介護負担軽減も、精神的サポートも、制度だけでは完結しません。
大田区の取り組みは、「支援の担い手」を拡げることで、“地域全体がケアを担う社会”を実現しようとしています。
認知症の地域包括ケアとは、制度でも、事業でもなく、
「人と人との関係性を支える文化」のこと。
その文化が根づく街にこそ、真の安心が生まれるのです。
大田区鵜の木の訪問看護・訪問リハビリ ─ 大田ケア訪問看護ステーション
大田ケア訪問看護ステーションでは、患者さんがご自宅で自分らしく療養生活を送ることができるように、訪問看護師とリハビリ専門職が連携して支援を行っています。
私たちの強みは、ご利用者さまのわずかな体調や食欲の変化、生活リズムの変動を丁寧に見逃さずキャッチし、必要な支援をすぐにご家族と共有できる体制を整えている点にあります。栄養管理、症状緩和、体力維持のリハビリを軸に、ご家族とチームで在宅ケアを進めています。
在宅ケアの土台は「対話による心のつながり」
ご利用者さんにとって、在宅での療養生活には体調の変化や生活上の不安、栄養・水分管理の難しさなど、避けて通れない課題が存在します。大田ケアの訪問看護師は、ご利用者さんの体調や精神面に加え、食事摂取状況や栄養バランス、排便や水分管理まで細やかに観察し、必要に応じて看護計画を柔軟に調整します。
在宅ケアでは、服薬管理の徹底、生活リズムの安定化、慢性疾患のコントロールなど、個々の症状に合わせた対応が求められます。そのため、訪問看護師が日々の状態をきめ細かく把握し、主治医や管理栄養士、リハビリスタッフと連携することで、安心して療養を続けられる環境を整えています。
さらにリハビリスタッフも、ご利用者さんの「日常生活を少しでも快適に過ごしたい」「体力を維持・回復したい」といった目標を共有し、その実現に向けた支援を行います。その過程でご家族さまにも情報を丁寧に共有し、ケアチームの一員として主体的に関われるようサポートしています。こうした体制によって、ご利用者さんとご家族さまがともに安心して在宅生活を続けられる仕組みを築いています。
24時間365日対応可能な安心の連絡体制
大田ケアでは、緊急時にも対応できるよう24時間365日体制の連絡窓口を完備。たとえば、胃瘻のトラブルや急な嘔吐・下痢、脱水が懸念される場合にも、看護師が迅速に受診先の案内や応急処置のアドバイスを行います。
訪問開始時に、緊急時の対応フローを事前にご家族へ明確に説明し、夜間や休日にも慌てず冷静に行動できるようサポートします。
ご家族も安心して関わるケアの仕組み
訪問スケジュールや看護計画の内容については、患者さんの生活スタイルやご家族の都合を丁寧に伺いながら調整。ご家族が果たす役割も明確にし、「無理なく・安心して支えることができる」体制づくりを目指します。
「自分らしく、生きる」を一つひとつ増やす
療養生活では、「食べること」「動くこと」「人と話すこと」が失われがちですが、大田ケアでは、そうした日常の一つひとつを大切に支えています。訪問看護と訪問リハビリが連携し、ご利用者さんの「その人らしさ」を尊重しながら、自宅で安心して過ごせる日々を創造します。
「治療が終わったけど食事に不安がある」「体力が戻らなくて外に出るのが億劫」「家族がどうサポートすればいいか分からない」──そんな時は、どうぞお気軽にご相談ください。大田ケアのチームが、一緒にその一歩を支えてまいります。
FAQ:よくある疑問にQ&A形式で回答
Q. 訪問看護サービスを利用するにはどうすればよいですか?
A. ご利用を希望される場合は、まずかかりつけ医または地域包括支援センター、居宅介護支援事業所を通じて要介護認定の申請を行ってください。要介護認定がおりた後、ケアマネジャーがケアプランを作成し、そのプランに基づいてサービスを提供します。直接当ステーションにご連絡いただいても手続きの流れをご案内できますので、お気軽にお問い合わせください。
Q. 週に何回、何時間利用できますか?
A. 訪問看護の頻度や時間は、ケアプランで決定します。通常は週に1~3回、1回あたり30分から90分程度が目安ですが、症状の度合いやご家族さまのご希望によって柔軟に調整可能です。
Q. 料金の自己負担はいくらですか?
A. 介護保険をご利用の場合は、要介護度に応じて自己負担が原則1〜3割となります。医療保険適用の訪問看護では、医師の指示で行う注射や点滴なども保険診療としてカウントされ、ご負担額は医療保険の自己負担割合に準じます。詳しい費用については、お住まいの自治体やケアマネジャーとご相談のうえご案内差し上げます。
Q. 24時間対応は可能ですか?
A. 大田ケアでは夜間・休日のオンコール体制を整えており、急な痛みの悪化や呼吸困難などの緊急事態にも電話でのご相談を受け付けています。緊急度が高いと判断した場合は、訪問看護師が緊急訪問を行い、一次的な対応を実施します。
Q. 自宅に必要な福祉用具はどう手配すればよいですか?
A. ケアマネジャーと連携し、手すりやスロープ、ポータブルトイレ、シャワーチェアなどの福祉用具を介護保険サービスでレンタルできます。大田ケアのスタッフがご自宅を訪問して適切な配置や使い方をアドバイスし、安心・安全な環境づくりをサポートします。
Q. 医師との連携はどのように行われますか?
A. 訪問看護師は定期的にバイタルサインを記録し、症状の変化を詳細に把握して医師に報告します。必要に応じて医師の指示を取り付け、薬剤の調整や注射管理を行うほか、電話やオンラインでの迅速な連絡体制を整えています。
Q. アドバンス・ケア・プランニング(ACP)はどのように進めますか?
A. ACPでは、医師が予後予測を説明し、延命治療の希望や最期の過ごし方についてご利用者さんの意思を整理します。大田ケアのチームは、訪問時にみなさまのお気持ちを伺いながら、その意思が尊重されるようサポートします。
Q. 申し込み後、どのくらいで訪問が始まりますか?
A. 必要書類が整い次第、通常は1週間以内に初回訪問を設定します。急ぎの場合は調整してより早い開始も可能ですので、ご希望があればご相談ください。
■看護・リハビリスタッフによる個別相談(無料)を予約する
https://otacare.com/otoiawase/
*お問合せフォームに、「個別相談希望」とご記載ください。折り返しご対応させていただきます
■大田ケアのパンフレットを見る
https://otacare.com/news/20250412/
☐私たちと一緒に働きませんか?採用情報を確認する
https://otacare.com/rikuru-to/
*看護・リハビリスタッフともに積極的に受け付けております
☐スタッフインタビューを見る
https://otacare.com/team/