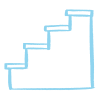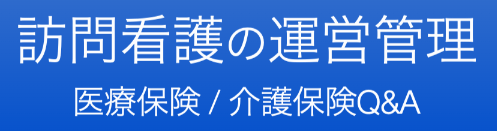Contents
なぜ今、精神科訪問看護が家族に必要なのか
ご家族の誰かが精神疾患を抱えたとき、最も近くで支える存在である家族は、時に強い不安と孤独を感じます。一方で、ご本人もまた、「家族に迷惑をかけているのではないか」「自分は社会に戻れるのか」といった不安や罪悪感を抱えがちです。家族も本人も、それぞれの立場で苦しみながら支え合おうとしています。症状の波や再発への心配、服薬や受診の管理、そして周囲の理解を得にくい現実。そうした日々のなかで、支援する側の家族自身が疲弊してしまうことも少なくありません。精神疾患は「本人の病気」であると同時に、「家族の生活全体に影響する病」とも言えるのです。
家族の孤立が進む現代社会
現代社会では、精神疾患に関する偏見や誤解がいまだ根強く残っています。近隣とのつながりが薄れ、家族の介護や看病が「家庭の中だけで完結してしまう」傾向も強まっています。特に統合失調症やうつ病、双極性障害などの精神疾患は、外見ではわかりにくく、周囲から理解を得にくい病気です。そのため、「誰にも相談できない」「家族でなんとかしなければ」と思い詰めてしまう方も多いのではないでしょうか。同時に、病気と向き合うご本人も、「理解してもらえない」「話しても信じてもらえない」と感じ、外の世界との距離を感じやすくなります。精神科訪問看護は、こうした“心の孤立”を少しずつ和らげる役割も担っています。
実際に、精神科病院から退院した後の生活を支える社会資源は、身体疾患と比べるとまだ十分とは言えません。訪問介護やデイサービスが身体障害に特化して整備されてきた一方で、精神疾患を対象とした地域支援の仕組みは、ようやく近年になって整い始めた段階です。こうした状況の中で、精神科訪問看護は、ご本人だけでなく「支える家族」にとっても大きな支えとなる存在になりつつあります。
精神科訪問看護が生まれた背景
精神科訪問看護は、長期入院を余儀なくされていた精神疾患の方々が、地域で安心して生活を送るための支援として始まりました。日本では2000年代に入り、医療政策として「精神科病床の削減」と「地域移行の推進」が進められています。入院中心の治療から、地域での生活支援を重視する方向へとシフトしているのです。
しかし、退院してもすぐに社会生活を安定させることは簡単ではありません。服薬管理の難しさや、再発への不安、人間関係のストレスなど、退院後こそ支援が必要な時期が続きます。精神科訪問看護は、そうした“地域で生きる”ためのサポートを担う存在として、医療と生活の間に立つ役割を果たしています。
家族が支える限界と、訪問看護の存在意義
多くのご家族さまは、「自分たちでなんとかしなければ」と頑張り続けます。しかし、病状が安定しない時期には、話しかけても反応がない、時に怒りっぽくなる、あるいは全く外出しなくなるなど、対応が難しい場面もあります。そうしたとき、専門知識や経験を持つ第三者が家庭に入ることで、ご家族さまの負担が大きく軽減されることがあります。
精神科訪問看護のスタッフは、ただ病状を観察するだけでなく、「ご家族さまの支援者」としても関わります。また、ご本人さまにとっても、訪問看護師は「家族とは違う安心できる第三者」として関わる存在です。家族には話しにくい思いも、看護師には素直に打ち明けられることがあります。そうした“心の逃げ場”があることで、回復へのステップを踏み出せる方も少なくありません。
看護師が定期的に訪問し、ご本人の服薬や睡眠、食事などの生活リズムを整えながら、ご家族さまにも相談や助言を行います。ときには、ご家族さまが抱える「もう限界かもしれない」という思いに寄り添い、次の一歩を一緒に考えることもあります。精神科訪問看護とは、本人の支援だけでなく、家族全体の心の安定を支える医療サービスなのです。
「支えられる側」から「支え合う側」へ
訪問看護を利用することに抵抗を感じるご家族さまも少なくありません。ご本人さまの中にも、「他人に迷惑をかけたくない」「家に来られるのは気が重い」と感じる方がいます。しかし、訪問看護は“病気を監視する”ためではなく、“一緒に暮らしを整える”ための支援です。看護師は、あなたのペースを大切にしながら、無理のない関わりを続けていきます。
「他人を家に入れること」や「家族の問題を見せること」に戸惑う方も多いでしょう。しかし、支援を受けることは決して恥ずかしいことではありません。むしろ、ご家族さまが長く穏やかに暮らすためには、外部の力を上手に借りることが大切です。
精神疾患のケアは、医療・福祉・地域が連携して支えるべきものであり、ご家族さまだけに背負わせるものではありません。訪問看護の存在は、「家族の限界を支える制度的な安全網」として機能します。そして、それをきっかけに、支える家族自身が安心して日々を過ごせるようになるのです。
精神科訪問看護とは ― 一般の訪問看護との違い
「訪問看護」という言葉を耳にすると、多くの方はまず「高齢者や身体の病気のある方が利用するサービス」という印象をお持ちになるかもしれません。確かに、在宅医療の分野では、がんや脳梗塞、糖尿病などの身体疾患を抱える方が、自宅での療養を続けるために訪問看護を利用するケースが一般的です。
しかし、精神科訪問看護はそれとは目的も内容も異なります。ここでは、精神科訪問看護がどのような支援なのか、どのような人が利用できるのか、そして一般の訪問看護との違いについて詳しくご説明いたします。
精神科訪問看護の目的 ― 「病気を治す」から「生活を整える」へ
精神科訪問看護の最大の特徴は、「症状の改善」だけでなく、「生活の安定と継続」を重視している点にあります。
精神疾患は、風邪のように完治して終わる病気ではなく、長期的に向き合っていく必要があります。症状が落ち着いても、ストレスや環境の変化によって再発することも珍しくありません。そのため、薬をきちんと飲み続けること、生活リズムを整えること、人との関係を少しずつ取り戻すことなど、日常の小さな積み重ねがとても大切になります。
訪問看護師は、そうした「日常生活の回復」を支えるパートナーとして関わります。症状のあるときも、落ち着いているときも、看護師は“あなたの今”を尊重しながら関わります。「今日は話したくない」という日もあって構いません。その沈黙の中にも寄り添い、回復のリズムを一緒に整えていくのが、精神科訪問看護の特徴です。看護師がご自宅に訪問し、ご本人の様子を見守りながら、服薬管理、食事や睡眠の状況確認、コミュニケーションのサポートなどを行います。ときには外出や買い物、地域活動への参加を一緒に支援することもあります。
つまり、精神科訪問看護は、「生活の安定」=「再発予防」を目指すケアなのです。
利用できる制度 ― 医療保険・自立支援医療制度の対象
精神科訪問看護は、主に医療保険の対象です。身体疾患の訪問看護のように、介護保険を利用するケースは比較的少なく、通院中の精神科主治医が発行する「訪問看護指示書」に基づいてサービスが始まります。
また、精神疾患のある方の多くは「自立支援医療制度(精神通院医療)」の対象になります。この制度を利用すると、自己負担が原則1割となり、経済的な負担を大きく軽減できます。所得に応じた上限額も設定されているため、安心して継続的に利用できる仕組みです。
訪問看護を受けるためには、まず主治医と相談し、「訪問看護が必要」と判断された場合にステーションを紹介してもらうことが一般的です。
対象となる疾患と支援内容
精神科訪問看護は、さまざまな精神疾患に対応しています。代表的なものとして、以下のような疾患が挙げられます。
- 統合失調症
- うつ病・双極性障害(躁うつ病)
- 不安障害・パニック障害
- 強迫性障害(OCD)
- 摂食障害(拒食・過食)
- アルコール・薬物依存症
- 発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)
- 認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)
これらの疾患では、症状の波があり、気分の変動や意欲の低下、対人関係の難しさなどが生活に影響を与えます。看護師は、病状の観察や服薬確認を行うとともに、日々の変化を見逃さないようにサポートします。
特に統合失調症や双極性障害では、「服薬の継続」が安定の鍵になります。しかし、ご本人さまが服薬を拒否する、忘れてしまうなどの問題も多く、管理するのは大変です。訪問看護師が第三者として関わることで、ご本人さまの服薬への理解を促し、自然な形で生活に取り入れていく支援が可能になります。
家族支援としての訪問看護
精神疾患を抱える方の支援は、ご家族さまの協力なくしてなりたちません。しかし、ご家族さまが疲れきってしまうと、支援そのものが続かなくなってしまいます。訪問看護師は、ご家族さまのケアも重要な役割と考えています。
たとえば、「どう声をかけたらよいかわからない」「本人に腹を立ててしまう」といったご家族さまの悩みに対して、看護師が具体的なコミュニケーション方法を助言します。また、心理的負担を軽減するために、必要に応じて家族面談や支援機関との調整を行います。
精神科訪問看護は、本人と家族の両方を支える看護なのです。家族のサポートを通して、ご本人が「自分も支えられている」「理解してもらえている」と感じることが、安心や自己肯定感の回復につながります。つまり、家族と本人の両方が支えられることで、生活全体が安定していくのです。
大田区における精神科訪問看護の現状と特徴
大田区の精神科訪問看護の特性
東京都大田区は、東京23区の中でも面積が広く、住宅地と商業地が共存する地域として知られています。蒲田・大森・池上・田園調布・羽田といったエリアごとに特色があり、人口も約74万人を超える大都市の一つです。その一方で、地域の中には精神疾患を抱える方や、その家族が静かに支援を求めているケースも多くあります。こうした背景のもと、精神科訪問看護の重要性が年々高まっています。
精神科訪問看護は、病院やクリニックでの通院治療を支える「地域医療の要」として、徐々に地域に浸透し始めています。大田区には現在、訪問看護ステーションが多数存在し、そのうち精神科に対応している事業所も着実に増えています。これは、国や都が掲げる「地域包括ケア」の理念に沿って、精神疾患を持つ人々が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援体制を整えてきた成果でもあります。
また、近年では高齢化が進んでいる一方で、うつ病や発達障害、不安障害など、若年層から中高年層にかけての精神疾患も増加傾向にあります。家庭内での孤立や仕事のストレス、介護との両立など、現代的な問題が複雑に絡み合う中で、精神科訪問看護は「医療と生活の橋渡し」として欠かせない存在になっています。
大田区の精神保健福祉相談(こころの相談)
さらに、大田区では行政の取り組みも進んでおり、保健所や精神保健福祉センター、地域包括支援センターなどが連携して、精神疾患を抱える方への相談体制を整備しています。訪問看護ステーションはこれらの機関と連携しながら、必要に応じて医療・福祉・就労支援などの情報をつなぐ役割を担っています。このような地域全体の連携が、精神科訪問看護の質を支えているのです。
精神疾患は長期的な支援を必要とする病気です。だからこそ、「地域にどれだけ安心して相談できる拠点があるか」が、本人と家族の生活の質を大きく左右します。
訪問看護ステーションの選び方・見るべきポイント
精神科訪問看護を検討するご家族にとって、最も気になるのは「どのステーションにお願いすれば安心なのか」という点ではないでしょうか。インターネット上には多くの情報があり、評判や口コミを見ても判断が難しいと感じる方が多いようです。ここでは、精神科訪問看護ステーションを選ぶ際に注目しておくべきポイントを、現場の視点も交えながら詳しくご説明いたします。
精神科訪問看護は、どの事業所を選ぶかによって支援の内容や雰囲気が大きく異なります。なぜなら、訪問する看護師の経験や人柄、事業所の方針によって「支援の方向性」や「家族との関わり方」が変わるからです。そのため、単に「近い場所にあるから」「ホームページがきれいだから」といった理由だけで選ぶのではなく、自分たちの家族に合った支援をしてくれるかどうかを丁寧に見極めることが大切です。
まず確認すべきは、スタッフ体制と専門性です。精神科訪問看護では、精神科での勤務経験を持つ看護師や、精神科認定看護師、公認心理師、精神保健福祉士などの専門職が関わることで、支援の質が大きく高まります。精神疾患は症状の波があり、危機的な状況になることもあるため、精神科特有の対応に慣れているスタッフがいることは安心材料になります。もし可能であれば、初回相談の際に「どのような看護師が訪問してくださるのか」「どのような経験を持っているのか」を確認してみるとよいでしょう。
また、24時間対応や緊急時の支援体制が整っているかどうかも大切なポイントです。精神疾患は、夜間や休日に急な不安や混乱が起こることがあります。そうしたとき、緊急連絡先があるのか、オンコール体制があるのかを事前に確認しておくことで、いざという時に安心して相談できます。すべての事業所が24時間対応をしているわけではありませんが、対応できない場合でも「どのように連携を取るか」を説明してくれるところは信頼できます。
さらに、精神科訪問看護において重要なのが、家族支援の姿勢です。訪問看護はご本人さまだけでなく、ご家族さまを支えるためのサービスでもあります。看護師が訪問時にご家族さまの話を丁寧に聞き、悩みを共有してくれるかどうかは、支援の満足度に直結します。「本人の様子だけでなく、家族の話も聞いてもらえた」「看護師さんがいることで、自分も安心できた」と感じられるかどうかが、良いステーションの目安になるでしょう。
また、利用を考える際には、費用や保険制度の説明が明確であるかも確認しておきたい点です。精神科訪問看護は医療保険の対象ですが、自己負担額や支払い方法は事業所によって異なります。説明が曖昧なまま契約を進めてしまうと、後から想定外の費用がかかることもあります。初回相談の際に「どの保険が使えるのか」「自立支援医療制度は適用されるか」「1回あたり、または1か月あたりの費用はどの程度か」など、具体的に尋ねておくと安心です。
信頼できるステーションかどうかを見極めるためには、口コミや評判も参考になります。インターネット上のレビューだけでなく、地域包括支援センターや医療機関、精神保健福祉センターなどから情報を得ることも有効です。特に「対応が丁寧」「相談しやすい」「家族の話を聞いてくれる」といった評判が多いステーションは、安心して依頼できる傾向があります。ただし、口コミには個人の感想も含まれますので、あくまで参考情報として捉え、最終的には実際に話を聞いた印象を大切にすることをおすすめします。
訪問看護ステーションを選ぶ際のもう一つの視点として、契約前に見学や相談ができるかどうかも重要です。事業所によっては、契約前に担当看護師と面談したり、訪問内容について説明を受けたりする機会を設けています。このとき、スタッフの言葉遣いや態度、説明の丁寧さなどから、その事業所の雰囲気を感じ取ることができます。精神疾患を抱えるご本人やご家族さまにとって、相性の良い支援者と出会うことは何より大切です。焦らず、複数の事業所を比較して検討するのがよいでしょう。
費用・制度・利用の流れ
精神科訪問看護を利用したいと考えたとき、多くのご家族さまが最初に気にされるのは「費用の負担」と「利用までの流れ」ではないでしょうか。医療サービスである以上、手続きや制度の理解は少し複雑に感じられるかもしれませんが、実際には多くの方が保険制度を利用しながら、比較的負担の少ない形でサービスを受けています。ここでは、利用を開始するまでの一連の流れと、費用の仕組み、使える制度についてご説明いたします。
利用開始までの基本的な流れ
精神科訪問看護は、主治医の「訪問看護指示書」に基づいて行われる医療サービスです。そのため、まず最初のステップは「支援者や医療機関への相談」です。ケアマネジャーや気になってい訪問看護ステーション、またかかりつけの精神科や心療内科の医師に「訪問看護を利用してみたい」と伝えてみてください。そこで次のステップについての助言を受けることができます。
次に、訪問看護ステーションとの面談や契約を行います。初回面談では、ご本人さまの状態や生活の様子、家族の希望などを丁寧に聞き取り、支援内容をすり合わせます。初回訪問日が決まったら、いよいよ自宅での支援がスタートします。
訪問開始後は、看護師が主治医やその他支援者等と連携を取りながら、定期的に報告を行います。必要に応じて、治療方針の調整や訪問頻度の変更が行われることもあります。
費用には医療保険が適用されます
精神科訪問看護は、基本的に医療保険の対象です。そのため、自己負担は通常3割となります。ただし、多くの方は「自立支援医療制度(精神通院医療)」を利用することで、自己負担が1割に軽減されます。この制度を利用している場合、訪問看護の費用も同じく1割負担となるため、経済的な負担を大きく抑えることができます。
たとえば、1回の訪問にかかる費用が約5,000円だとすると、自立支援医療を利用すれば自己負担は約500円程度になります。週に2回の訪問を受けた場合でも、1か月あたりの自己負担は4,000〜5,000円前後に収まるケースが多いです。費用は訪問時間や回数、加算項目(24時間体制加算など)によって変わりますが、制度を上手に利用することで、長期的な支援を無理なく続けることができます。
なお、生活保護を受けている場合は、訪問看護の費用は全額公費で賄われ、自己負担はありません。その他、所得に応じて「高額療養費制度」や「重度心身障害者医療費助成制度」などを併用できる場合もあります。地域によっては、区独自の助成制度があることもありますので、大田区にお住まいの場合は、区役所や保健所に確認してみるとよいでしょう。
自立支援医療制度の利用方法
自立支援医療制度を利用するためには、いくつかの手続きが必要です。まず、主治医に「自立支援医療の申請書」を書いてもらい、診断書を添付して区役所の担当窓口に提出します。審査の結果、認定されると「自立支援医療受給者証」が交付されます。この受給者証を医療機関や訪問看護ステーションに提示することで、自己負担が1割に軽減されます。
この制度は1年ごとの更新が必要ですが、更新の際も手続きは比較的簡単です。収入に応じた月額の自己負担上限額も設定されるため、経済的な不安を感じることなく、継続的に支援を受けることが可能です。
訪問頻度と利用時間の目安
訪問看護の頻度は、本人の状態や生活状況に応じて決まります。一般的には、週1回から2回程度の訪問が多く、1回あたりの訪問時間は30分から1時間前後ですが、状態が不安定な方は週に複数回の訪問でサポートを受けることもあります。主治医と看護師が連携しながら、必要に応じて柔軟に調整できる点が精神科訪問看護の強みです。
費用シミュレーションの一例
たとえば、統合失調症で通院中の方が週に2回、1回1時間の訪問看護を利用する場合を想定してみましょう。1回あたりの費用が約5,000円とすると、月8回で4万円になります。自立支援医療を利用すれば自己負担は1割となり、実際に支払う額は約4,000円程度です。さらに高額療養費制度の上限に達した場合、それ以上の負担は免除されます。このように、制度を活用することで、長期的な利用も現実的な費用で続けることができます。
契約後の流れとサポート体制
契約が完了すると、訪問看護師が定期的に家庭を訪れ、症状や生活の様子を観察しながら支援を行います。初回訪問では、看護師がご本人さまの状態や生活リズムを丁寧に把握し、ご家族さまと一緒に支援目標を立てます。
また、訪問看護を続けていく中で、ご本人さまやご家族さまの気持ちが変化した場合には、いつでも支援内容を見直すことができます。「最近は落ち着いてきたので訪問を減らしたい」「不安が強くなってきたので回数を増やしたい」といった希望にも柔軟に対応してもらえます。定期的に看護師と振り返りを行いながら、そのときどきに合った形で支援を受けられるのが、この制度の大きな魅力です。
精神科訪問看護の利用は、単に医療行為を受けるということではなく、「家庭の中に安心を取り戻す」ための一歩でもあります。費用の不安や制度の複雑さに戸惑う方もいらっしゃいますが、多くの支援制度を活用することで、思っている以上に利用しやすい仕組みになっています。
精神科訪問看護のよくある質問(FAQ)
精神科訪問看護は、まだ一般的な認知度が高いとは言えない分野です。そのため、「どんなことをしてもらえるのか」「どんな人が来るのか」「どうやって申し込むのか」など、利用を検討する際に多くの疑問が浮かぶのは当然のことです。ここでは、実際にご家族から寄せられることの多い質問をもとに、一つひとつ丁寧にお答えいたします。
Q. 精神科訪問看護とカウンセリングはどう違うのですか?
精神科訪問看護は、医師の指示書に基づいて看護師が自宅を訪問し、医療的な視点から支援を行うものです。服薬の確認や体調の観察、生活リズムの調整、再発予防のための助言などを行い、必要に応じて主治医と連携します。一方、カウンセリングは心理的な支援を中心とした対話的なサポートで、臨床心理士やカウンセラーが担当します。両者は目的が異なりますが、併用することでより効果的な支援が期待できます。
Q. 訪問の頻度や時間はどのくらいですか?
訪問の頻度は、ご本人さまの状態や生活状況によって異なります。一般的には週に1〜2回、1回あたり30分から1時間ほどの訪問が多いです。症状が安定している方は月に数回、逆に不安定な時期には週に複数回訪問することもあります。主治医や看護師と相談しながら、無理のないペースで支援を受けることができます。
Q. 夜間や休日にも対応してもらえますか?
ステーションによっては24時間対応の体制を整えているところもあります。夜間や休日に急な不調が起きた場合、電話で相談できたり、必要に応じて緊急訪問が行われることもあります。
Q. 入院中でも訪問看護を受けられますか?
原則として、訪問看護は自宅での生活を支援するサービスのため、入院中には利用できません。ただし、退院前から今後の生活に向けて「退院前カンファレンス」に参加することがあり、退院後スムーズに在宅生活へ移行できるよう準備を進めることが可能です。
Q. 家族もサポートしてもらえるのでしょうか?
はい。精神科訪問看護では、ご家族さまの支援をとても大切にしています。看護師はご家族さまの悩みや不安を聞き取り、接し方の工夫や支援の方法を一緒に考えます。必要に応じて家族面談を行い、支援機関や相談窓口の情報提供も行います。訪問看護は、ご本人さまに加えて「家族も支える」仕組みとして存在しています。
Q. 利用をやめたいときはどうすればよいですか?
訪問看護はいつでも中止や変更が可能です。体調が安定してきた場合や支援の方向性を見直したい場合には、看護師や主治医に相談してください。話し合いの上で、回数を減らしたり、一時的に休止したりすることもできます。ご利用者さまの意思が最も尊重される仕組みです。
このように、精神科訪問看護は制度的にも心理的にも利用しやすいサービスへと進化しています。不安な点があれば、まずはステーションに問い合わせてみてください。誠実な対応をしてくれる事業所ほど、長く信頼して付き合えるパートナーになります。
まとめ
精神科訪問看護を通じて見えてくるのは、「支える家族もまた支援を必要としている」という事実です。ご家族さまは最も近い存在だからこそ、ご本人さまの苦しみを受け止め、時に自分を責めてしまうこともあります。しかし、ご家族さまが疲れ切ってしまえば、支援そのものが続かなくなってしまいます。訪問看護は、そうしたご本人さま、ご家族のさま心を支え直すための大切な仕組みです。
訪問看護の看護師は、単に医療行為を行う専門職ではありません。家族の中に入って話を聞き、共に悩み、共に考える存在です。「誰かが自分たちを理解してくれている」という感覚は、何よりの安心になります。孤立を防ぐことは、病気の回復にもつながります。支援を受けることは、決して弱さではなく、最善の選択なのです。
大田区では、行政・医療・福祉が連携し、精神疾患を抱える方や家族が地域の中で安心して暮らせる環境づくりが進んでいます。地域包括支援センターや保健所、訪問看護ステーションがつながることで、支援の輪は着実に広がっています。こうした地域の取り組みは、「家族もまた支えられる社会」への第一歩です。
これから訪問看護を検討される方へお伝えしたいのは、「迷ったら、まずは相談してみてください」ということです。初めての一歩は勇気がいりますが、その一歩の先には、ご本人さまとご家族さまを支える人たちが待っています。病気や支援に関する悩みを一人で抱え込まず、どうか地域の支援を頼ってください。
情報源・出典元データなど
専門機関
- 精神科訪問看護に関する制度全般: 厚生労働省「精神科訪問看護の手引き(令和5年改訂版)」
- 自立支援医療(精神通院医療)制度の概要: 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)」
- 訪問看護に関する診療報酬・保険制度の位置づけ: 厚生労働省「訪問看護制度の概要」
- 地域移行支援・精神保健医療改革の方向性: 厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」
学術論文
- アドバンス・ケア・プランニング(ACP)に関する看護研究(J-STAGE)
- Patient-Controlled Analgesia in Palliative Care: Exploratory Scoping Review(2025)
- 在宅ホスピスにおける家族介護者の負担研究(J-HOPE)
- Mindfulness in End-of-Life Care(2024, Sciencedirect)
- Resilience-Building in Palliative-Care Professionals: Scoping Review(BMJ Supportive & Palliative Care 2025)
その他、Webサイト
■看護・リハビリスタッフによる個別相談(無料)を予約する
https://otacare.com/otoiawase/
*お問合せフォームに、「個別相談希望」とご記載ください。折り返しご対応させていただきます
■大田ケアのパンフレットを見る
https://otacare.com/news/20250412/
☐私たちと一緒に働きませんか?採用情報を確認する
https://otacare.com/rikuru-to/
*看護・リハビリスタッフともに積極的に受け付けております
☐スタッフインタビューを見る
https://otacare.com/team/