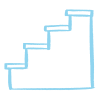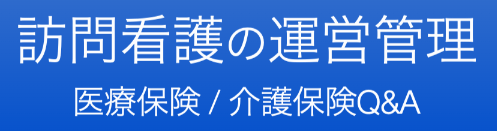脳卒中は突然起こり、麻痺・言語障害・嚥下障害などの後遺症が残ることが多い疾患で、退院後の自宅生活では継続的な健康管理とリハビリが欠かせません。訪問看護では再発予防や健康管理を行い、訪問リハビリでは歩行訓練・ADL訓練など機能回復を支えます。本記事では、脳卒中の基礎知識から自宅リハビリの進め方、訪問サービスのメリットを解説します。
Contents
脳卒中の基礎知識
脳卒中とは
日本では「脳卒中=突然倒れて半身まひになる病気」というイメージが定着しているものの、その正体はひとつの病気ではありません。
脳卒中とは、脳の血管が詰まる脳梗塞、破れる脳出血、くも膜下出血の3つの総称を指します。発症後の死亡率や後遺症の重さは依然として高く、循環器病対策基本法が掲げる国民的課題のひとつです。
2023年、日本脳卒中データバンクには約1万8000例が登録され、病型別の治療内容や転帰が克明に記録されました。
脳卒中と脳梗塞は何が違うのか
脳卒中は“発症様式”で分類します。血管が詰まる脳梗塞が全体の8割前後、破裂による脳出血とくも膜下出血が残りを占めます。脳梗塞という言葉はしばしば脳卒中と同義で使われますが、厳密には“脳卒中の中で最も⼀般的な病型”という位置づけです。
冠動脈で起こるのが心筋梗塞、脳血管で起こるのが脳梗塞。血管の閉塞という病態は同じでも、ダメージを受ける臓器が異なります。血圧や糖尿病、脂質異常、心房細動などのリスク因子は共通しており、生活習慣病と循環器病の連鎖が背景にあります。
脳梗塞による脳卒中の原因・病態・症候
脳梗塞は血栓が血管を閉塞し、脳組織に酸素と栄養が届かなくなる虚血性障害です。発症直後から毎分200万個のニューロンが失われるといわれ、「Time is Brain」という国際標語が示す通り、分単位の治療が運命を分けます。脳出血は高血圧などで傷んだ細小血管が破裂し、血腫が神経を圧迫します。くも膜下出血は動脈瘤破裂による蜘蛛の巣下腔の出血で、激烈な頭痛と嘔吐の症状が典型的です。
症候は片麻痺、感覚障害、構音障害、失語、視覚障害、意識障害などですが、「顔・腕・言葉」のいずれかが急におかしいときはただちに119番これが基本行動になります。
脳卒中の治療――“ゴールデンタイム”を活かす急性期医療
発症後4時間半以内であれば静注tPA(アルテプラーゼ/テネクトプラーゼ)による血栓溶解療法、6時間(頸動脈閉塞は最長24時間)以内であればカテーテルを用いた血栓回収(機械的血栓除去術)が保険診療で標準化されています。脳出血には血腫除去術や定位深部血腫吸引、くも膜下出血にはクリッピング・コイル塞栓術が選択され、集中治療室での血圧・脳浮腫管理が不可欠です。急性期の治療方針とリハビリ計画を同時にデザインする“ストロークユニット”体制が、後遺症を大きく左右します。
脳卒中の後遺症と長期的視点
退院時までに「modified Rankin Scale(mRS)」0~2(自立歩行可能)を達成する割合は4~5割前後にとどまり、片麻痺や嚥下障害、高次脳機能障害、感情失禁、うつ・認知症などの後遺症が残るケースが少なくありません。
記憶・注意・遂行機能を含む認知障害は就労や家庭復帰を阻む大きな要因であり、早期からの作業療法・言語療法を通じた社会参加アプローチが必要です。
脳卒中の予防――一次・二次・三次の三層構造
一次予防は生活習慣の是正とハイリスク者の医療介入です。減塩(1日6g未満)、禁煙、節酒、運動(有酸素運動+筋トレ)、血圧130/80未満、HbA1c 7.0%未満、LDLコレステロール100mg/dL未満を“ニューノーマル”と捉え、心房細動に対しては抗凝固薬の適正使用を徹底します。
二次予防は抗血小板薬・抗凝固薬、スタチン、降圧薬、生活習慣介入を組み合わせ、再発率を年5%以下に抑え込む戦略です。
三次予防は後遺症の固定化と合併症(骨折・心血管イベント)の防止で、骨密度管理や転倒予防プログラムが含まれます。
若い人の脳梗塞、脳卒中――増加する“アンダー45”への処方箋
30~40代で発症する若年性脳梗塞は、頸動脈・椎骨動脈解離、もやもや病、抗リン脂質抗体症候群、先天性凝固異常、低用量ピルや妊娠に伴う血栓リスクなど、多岐にわたる原疾患が背景にあります。臨床の最前線では「原因によって再発予防策がまったく違う」ため、MRAや血液凝固系検査、遺伝子検査まで含めた精査が欠かせません。2025年5月の国内医師解説記事でも“若年層の症例増加傾向”が取り上げられています。
若年発症は就労や学業を直撃し、経済的・心理的負担が深刻化するため、職場復帰支援プログラムやピアサポートを組み込んだ包括的ケアが推奨されます。
脳卒中の前兆チェックリスト――“異変の兆し”を逃さない
以下の項目に「✔」がついたら、すぐに救急(119番)を要請してください。たとえ一時的に症状が回復しても、TIA(一過性脳虚血発作)の可能性があり、これは数分から1時間程度で症状が消えるものの、3か月以内に脳梗塞を発症するリスクが高いとされています。
□ 顔の片側が垂れる・ゆがむ
片方の口角が下がったり、笑顔をつくろうとしても左右で違いが出る。
□ 腕(手)の力が入らない・しびれる
片方の腕や手を半分上げると、すぐに下がってしまう/ピリピリ・チクチクした感覚がある。
□ 言葉が出にくい・ろれつが回らない
簡単な言葉(「おはよう」「ありがとう」など)を話そうとしてもうまく発音できない。
□ 片側の視野が見えにくい・急な視力低下
左右どちらかの目で見えにくさ、視界が欠ける、視力が急に落ちる。
□ 激しい頭痛が突然始まる
これまでにない激痛で、吐き気や嘔吐を伴うことが多い。
□ めまい・ふらつき・歩行困難
立っていられない/歩こうとするとふらふらして倒れそうになる。
□ 意識障害・混乱
ぼんやりしたり、周囲の人や場所がわからなくなる。
□ 強い吐き気・嘔吐
特に頭痛やめまいを伴う嘔吐は要注意です。
FASTサインの確認
- Face(顔):笑顔をつくって左右差がないか
- Arm(腕):両腕を上げてみて、どちらかが下がらないか
- Speech(言葉):簡単なフレーズを繰り返してみて、発音できるか
- Time(時間):1~3のどれかがおかしければ、迷わず119番
こうした症状が一過性に収まってもTIA(一過性脳虚血発作)の可能性があります。TIA後の48時間は脳梗塞に進展するリスクが高く、救急受診が推奨されます。FAST(Face, Arm, Speech, Time)を家族や職場に共有しておくことが最大の防波堤です。
脳卒中の訪問看護・訪問リハビリ――自宅に専門職を呼び込む時代
脳卒中の訪問看護・訪問リハビリの意義
回復期リハ病棟を経て在宅復帰した後、“維持期リハビリ”の質を決めるのは訪問看護師・理学療法士・作業療法士のチームワークです。近年の在宅脳血管疾患リハでは「多職種連携」により、ケアマネジャーと家族を巻き込んだ目標設定が主流になっています。
訪問看護はバイタルサイン管理、嚥下評価、痙縮コントロール、自己注射・服薬支援など医学的ケアを担い、リハスタッフは歩行訓練や上肢巧緻運動(“細かい手の動き”)、ADL指導(食事や着替え、歯みがき、トイレなど、毎日の暮らしにおける自立した生活のためのサポートのこと)を行います。
継続的な環境評価、段差解消、手すり設置、福祉用具導入がQOLを底上げし、再入院率を下げる鍵となります。
リハビリテーションでQOLを維持するコツ
脳卒中後の可塑性は“使った神経回路が強化される”という経験依存則に従います。したがって「早期・高頻度・課題指向型」の三原則が重要です。
作業療法では実際の日常行為(調理、パソコン操作)を課題化し、報酬系を刺激するゲーミフィケーションを組み込むことで自発練習を促進します。
言語リハでは失語症テレリハや発話流暢性を高めるメロディックイントネーション法がデジタル化され、遠隔でのセラピー継続が可能になりました。
歩行や理学療法リハビリテーションではロボティクスやFES(機能的電気刺激)のエビデンスが蓄積し、介護負担軽減と転倒リスク低減に寄与しています。
脳卒中経験者の自宅でのケアのコツ
浴室や玄関の段差、狭い動線、滑りやすい床材は転倒を招きます。介護保険の住宅改修費(20万円上限)を活用して、手すり設置や段差解消を計画することが先決です。高次脳機能障害を伴う場合は、冷蔵庫メモや音声アラームなどの“認知環境支援技術”が自立を補います。
嚥下障害にはテクスチャー調整食品、嚥下補助具、ポジショニングクッションが役立ち、口腔ケアを徹底することで誤嚥性肺炎のリスクを下げます。
介護者のレスパイトケアとして短期入所(ショートステイ)や訪問介護夜間対応型の併用も計画的に組み込みましょう。
脳卒中にともなう医療費と公的助成
厚生労働省の国民医療費概況によると、脳血管疾患の年間医療費は1兆8,142億円。高齢者医療の伸びとともに年々増加しています。
入院初月の自己負担は高額療養費制度で月6~9万円台に抑えられるものの、所得区分別の自己負担上限が段階的に引き上げられる検討がされており、一般所得層の外来上限は18,000円から28,000円へ改定の予定でした。
*2025年8月からの引き上げは見送りが決定しました。
脳卒中自体は指定難病の対象ではないため、「高額療養費」「医療費控除」「障害年金」「介護保険」「自立支援医療(精神)」など複数制度を組み合わせるのが現実的戦略です。重度後遺症で身体障害者手帳1・2級を取得すれば、所得税住民税控除や福祉タクシー券、公共料金減免なども活用できます。
治療費だけでなく、通院交通費、装具代、住宅改修費も医療費控除の対象になるケースがあるため、領収書の一元管理を徹底しましょう。
大田ケア訪問看護ステーションにおける脳卒中患者さん支援
大田ケア訪問看護ステーションは、2025年4月に誕生した地域密着型の訪問看護ステーションです。その理念「ぬくもりと優しさ ココロに寄り添う看護」のもと、脳卒中を発症をされた患者さんとご家族の「いつもの暮らし」を取り戻すために、専門的な看護・リハビリテーションを一体的に提供します。
病院退院後の不安や孤独感は想像以上に大きいもの。訪問看護師とリハビリセラピストが、「痛みやしびれへの対処」「日常を取り戻すための小さな目標設定」「再発防止のための生活習慣改善」まで、心を込めてサポートします。
脳卒中ケアの土台は「対話による心のつながり」
脳卒中ケアの土台には「対話による心のつながり」が欠かせません。訪問看護師は、発症からリハビリまでの経緯、患者さんご自身の不安やお悩み、あるいはご家族の日常の出来事に至るまで、時間をかけてじっくりと共有します。そのうえで、医師や薬剤師、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネジャーら多職種チームと密に連携し、最新のリハビリ計画や医療処置の方針を常にアップデート。たとえば嚥下障害があれば言語聴覚士など必要に応じて専門家を迅速に割り当て介入していきます。
脳卒中リハビリでは「できること」を一つひとつ増やす
脳卒中リハビリでは「できること」を一つひとつ増やすことがQOL向上の要です。大田ケアでは、訪問時の歩行練習や上肢機能訓練に加え、調理や買い物といった“実生活に即した課題”を取り入れることで、患者さん自身が「自分でやれた!」という達成感を得られるようプログラムを設計。さらに、認知障害や感情失禁といった高次脳機能障害には、環境調整(見やすいカレンダー設置や声かけタイミングの工夫)とともに、ご家族へのアドバイスを組み合わせることで二次的ストレスを減らし、安心して在宅生活を続けられる仕組みを整えています。
在宅ケアの要となる訪問看護では、バイタルチェック・創傷管理・排泄ケア・手足の痙縮コントロールなど医学的ケアを、訪問リハでは歩行・動作練習やADL(日常生活動作)指導を担います。またケアマネジャーやご家族とも共有しながら、目標設定と進捗確認を定期的に実施。住宅改修や福祉用具の導入提案も行い、段差解消や手すり設置で転倒リスクを抑制します。
経済的負担に関しては、訪問看護・訪問リハビリともに介護保険の適用下で自己負担は1から3割となります。脳卒中は指定難病には含まれませんが、高額療養費制度や医療費控除、障害者手帳の取得支援などをご案内し、ご家族の経済的負担をできる限り軽減します。
脳卒中患者さんとご家族の“これから”を共に描きます
訪問エリアは大田区を中心に、世田谷区・目黒区・品川区・川崎市の一部地域。住み慣れたご自宅で安心してリハビリを続けることで、退院後の再入院リスクを下げ、最終的には「自立した日常生活の再構築」を目指します。脳卒中後の生活設計や訪問看護・リハビリに関するご相談は、ぜひ大田ケア訪問看護ステーションまでお問い合わせください。
大田ケアは、医療的ケアとリハビリを通じて、脳卒中患者さんとご家族の“これから”を共に描きます。心に寄り添う訪問看護で、一日でも早く、ご自分らしい暮らしを取り戻しましょう。
脳卒中は「発症した瞬間から時間との戦い」が始まり、退院後も「生活期」という第二ラウンドが続きます。医療者・患者・家族・地域が同じ地図を共有し、途切れないサポートラインを張り巡らせる、それこそが後遺症を最小化し、誰もが自分らしい人生を取り戻す近道です。
情報源・出典元データなど
専門機関
- 日本脳卒中学会(The Japan Stroke Society) — 診療ガイドラインや学会声明、脳卒中データバンクなどを公開
- 日本脳卒中協会 — 市民向け啓発(FAST運動)、地域連携パス資料を提供
- 国立循環器病研究センター(NCVC) — 脳卒中治療・予防に関する最新研究と患者向け情報
- 厚生労働省・循環器病対策推進室 — 循環器病対策基本法関連資料、国民医療費・患者調査
- 世界保健機関(WHO) – Cardiovascular Diseases Programme — 国際統計・政策レポート
- 米国疾病予防管理センター(CDC) – Stroke Division — エビデンスに基づく予防・二次予防資料
学術論文
- Saver JL. Time Is Brain—Quantified. Stroke. 2006;37:263-266.
- Hacke W et al. Intravenous t-PA within 3 Hours. NEJM. 1995;333:1581-1587.
- Campbell BCV et al. Endovascular Therapy after Imaging Selection in Ischemic Stroke (EXTEND-IA). NEJM. 2015;372:1009-1018.
- Powers WJ et al. 2018 Guidelines for Early Management of Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2018;49:e46-e110.
- Toyoda K et al. J-STARS: Statins for Secondary Prevention in Japanese Patients. Stroke. 2015;46:367-373.
- Albers GW et al. Thrombectomy 6–16 Hours after Stroke (DEFUSE 3). NEJM. 2018;378:708-718.
その他、Webサイト
- e-ヘルスネット(厚生労働省) — 生活習慣病と脳卒中の一次予防解説
- 日本脳卒中データバンク公式サイト — 国内症例の統計速報・公開年報
- 国立循環器病研究センター「脳卒中予防10か条」 — 市民向け予防チェックリスト
- 日本生活習慣病予防協会 – 脳卒中特設ページ — 食事・運動・減塩の実践ヒント
- 日本脳卒中友の会/患者家族サポート団体 — 体験談、ピアサポートイベント情報
大田ケアに相談する、知る
■看護・リハビリスタッフによる個別相談(無料)を予約する
https://otacare.com/otoiawase/
*お問合せフォームに、「個別相談希望」とご記載ください。折り返しご対応させていただきます
■大田ケアのパンフレットを見る
https://otacare.com/news/20250412/
☐私たちと一緒に働きませんか?採用情報を確認する
https://otacare.com/rikuru-to/
*看護・リハビリスタッフともに積極的に受け付けております
☐スタッフインタビューを見る
https://otacare.com/team/
大田ケアのコンテンツが、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
大田ケア訪問看護ステーション
info@otacare.com